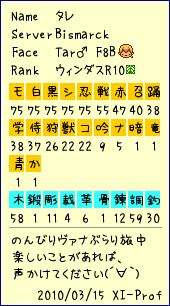| 2004 |
| 09,24 |
«雨の終わる場所»
「行ってきまーす」
無言の家に投げやりな声を上げながら、バサっと大きな傘を広げた。
バタンと後ろ手にドアを締め、そっと手にしたそれを見やる。
男物の紺のストライプが入った傘。
僕の視界をさっと傘の影が掠めた。
雨が時折バケツをひっくり返した感じで降り続く中、だんだんと濃い色へと変化していく制服をなんとか庇いながら、僕は道を急いだ。
−雨はキライ。
いつだってそうだった。
こんなちっちゃな傘だけじゃ、僕を庇うことなんて出来やしないのに。
それなのに、小さな傘の中に無理に体を押し込めて歩いてる自分の姿は、なんだか自分自身をそのまま象徴しているかのようで、いつだって胸が痛かったんだ。
そんな自分が、この雨を待つようになって、どれくらい経つんだろうか。
この傘の裏にこっそりとホワイトマジックで書かれたTのサイン。
流暢な筆記体で書かれたそれは、元々僕のものではなく、あの人のものだった。
黙って取ってきたわけではない。ただ、返す日を待ち続けているだけ。
それなのに、どこか大事なものを奪い取ってしまったような、そんな軽い罪の意識と底の知れない喪失感に、僕は自分を濡らしていた。
φ
それは、紫陽花の花の色が淡い青からグラデーションを変えていく頃のお話。
水曜日のAM11:00。
僕がコンビニでメンズノンノを立ち読みしていると、突然ガラス越しの景色がくすむのが見えた。
一瞬ピカッと光った後、数秒してから響く遠雷の音。
1km以上先の地点で鳴っている、そうわかっていても、なぜか逸る鼓動に追い立てられるように、僕は外へ出た。
そうだ、傘もってないじゃん。
引き返して傘を買ってこようと思った僕は、ふと傘立てに一本突っかけられていた傘に気が付いた。
店内はこんな不安定な天気だからか、客は誰一人いない。
そして、お店のカウンターには、、、あの人がいた。
水田と書かれたそのプレートの上に乗っている、ちょっとクセッ毛の栗色のショートと、田舎の少女のように少し赤い頬。
その笑顔がなんだか忘れられなくて、でも通ってるみたいなのはイヤで。
週に2回くらいここで立ち読みをするようになってからもう2ヶ月くらいだろうか。
やがて、彼女が「つばきちゃん」と呼ばれていることを知った。
平日の午前中という狭間の時間帯だからか、店員は彼女以外の姿はない。
すると、この「T」の文字がついた傘はやっぱり彼女なんだろうか。
大きな男物の傘に違和感を感じながらも、紺色のストライプが妙に洒落てて、そう考えるとセンスいいのかも、とちょっと思い直してみたりもして。
鼓動が早くなる。
そして−音が消えた。
気付けば、僕は学校でその傘をバサバサと広げ、雨を払っていた。
休み時間はとっくに終わっている。
次は数学の時間だから、適当に言い訳していけばいいだろ。
そう思う僕の頭の中からは、だんだんと傘の映像が薄れていく。
φ
それでも、家に帰る度、雨の日にそれを手にする度に、その日の出来事は何度もフラッシュバックしていた。
ただ、それはもうどこか現実味がない映像になっていて・・・。
彼女のことを想像する度に湧き上がる淡い炭酸水のような、そんなどこか甘酸っぱくも痛い気持ち。
しぼんでは膨らむその気持ちは、やっぱりこの傘のようで、僕は思わず傘の柄をぐっと握り締めた。
通り過ぎる車が時折あげる水しぶきを何度も避けながら、僕は目的地に辿り付く。
目の前に見えてくるいつものコンビニを見て、僕は一度傘をくるりと回した。
まだ、彼女がいない時間帯だった気がするし、多分大丈夫。
音を立てないようにそっと傘立てに近付き、くるくるとまわしながら傘を回す。
そして、傘を立て掛け、何食わぬ顔をして僕はコンビニに入った。
「いらっしゃいませー」
−ツバキちゃんの声だった。
僕は思わず舌打ちをして、雑誌コーナーへとターンする。
チラチラとレジを伺っていると、やがて彼女は店の奥へと声をかけ、エプロンを外し始めた。
どうやら交代の時間みたいだ。
ひょっとしたら傘に気付くかもしれない、そう思えば思うほど、しなくてもいいはずの緊張が妙に高まってきた。
「店長、お先に失礼しまーす」
入口付近で柔らかいメゾソプラノの声が響いたかと思うと、次の瞬間、
「あれ、この傘・・・」
そういいながら彼女は傘を手にする。
−やっぱりツバキちゃんのだよな・・・。
なぜか湧き上がるうれしい気持ちと、さみしい気持ち。
そして、色を濃くする罪悪感。
「わたしが探してた傘ありましたよー!よかった・・・」
「おお、あの傘か。よかったね、ツバキちゃん」
そんな会話を聞きながら、コンビニを出ようと雑誌を元の棚に戻した時、客が一人入ってきた。
メットをかぶった若い男の人だ。
「・・・あれ、タロウくん、何してるの?」
「へへ、迎えにきちゃった」
タロウくんと呼ばれたその男は、メットを脱ぎ、彼女の傘を手に取った。
「ん?ツバキこの傘って・・・」
「うん、今見つかったの。誰かが間違えて持ってったのを返してくれたんだと思う。
ほら、タロウくんのサインも入ってるし」
え・・・と呆気に取られている僕を尻目に、その男は傘をくるくると回しながら、
「お前に貸すとロクなもんじゃないよな・・・って時間ないし、そろそろ行くか」
と彼女を促し、店を出て行った。
φ
あれから数年が過ぎ・・・。
そんな苦い想いが一杯だった雨も、今ではそんなに気にならなくなった。
キライだった雨。
そして、やがてせつなさを増した雨。
それも、自分なりの防御壁になるんだとわかった今では、いい思い出って言えるようになったんだろうか。
ドアを締めながら、僕は傘を開く。
「ツバキ、そろそろ時間が・・・」
「あ、トーマくん、ちょっと待ってくれる?あなたの旅行券がまだテーブルに置いてあるわよ」
そんな彼女の言葉に、僕は慌てて傘を投げ出し、家の中に舞い戻る。
投げ出された傘の裏には、掠れた文字でTのイニシャルが僅かに残っていた。
無言の家に投げやりな声を上げながら、バサっと大きな傘を広げた。
バタンと後ろ手にドアを締め、そっと手にしたそれを見やる。
男物の紺のストライプが入った傘。
僕の視界をさっと傘の影が掠めた。
雨が時折バケツをひっくり返した感じで降り続く中、だんだんと濃い色へと変化していく制服をなんとか庇いながら、僕は道を急いだ。
−雨はキライ。
いつだってそうだった。
こんなちっちゃな傘だけじゃ、僕を庇うことなんて出来やしないのに。
それなのに、小さな傘の中に無理に体を押し込めて歩いてる自分の姿は、なんだか自分自身をそのまま象徴しているかのようで、いつだって胸が痛かったんだ。
そんな自分が、この雨を待つようになって、どれくらい経つんだろうか。
この傘の裏にこっそりとホワイトマジックで書かれたTのサイン。
流暢な筆記体で書かれたそれは、元々僕のものではなく、あの人のものだった。
黙って取ってきたわけではない。ただ、返す日を待ち続けているだけ。
それなのに、どこか大事なものを奪い取ってしまったような、そんな軽い罪の意識と底の知れない喪失感に、僕は自分を濡らしていた。
φ
それは、紫陽花の花の色が淡い青からグラデーションを変えていく頃のお話。
水曜日のAM11:00。
僕がコンビニでメンズノンノを立ち読みしていると、突然ガラス越しの景色がくすむのが見えた。
一瞬ピカッと光った後、数秒してから響く遠雷の音。
1km以上先の地点で鳴っている、そうわかっていても、なぜか逸る鼓動に追い立てられるように、僕は外へ出た。
そうだ、傘もってないじゃん。
引き返して傘を買ってこようと思った僕は、ふと傘立てに一本突っかけられていた傘に気が付いた。
店内はこんな不安定な天気だからか、客は誰一人いない。
そして、お店のカウンターには、、、あの人がいた。
水田と書かれたそのプレートの上に乗っている、ちょっとクセッ毛の栗色のショートと、田舎の少女のように少し赤い頬。
その笑顔がなんだか忘れられなくて、でも通ってるみたいなのはイヤで。
週に2回くらいここで立ち読みをするようになってからもう2ヶ月くらいだろうか。
やがて、彼女が「つばきちゃん」と呼ばれていることを知った。
平日の午前中という狭間の時間帯だからか、店員は彼女以外の姿はない。
すると、この「T」の文字がついた傘はやっぱり彼女なんだろうか。
大きな男物の傘に違和感を感じながらも、紺色のストライプが妙に洒落てて、そう考えるとセンスいいのかも、とちょっと思い直してみたりもして。
鼓動が早くなる。
そして−音が消えた。
気付けば、僕は学校でその傘をバサバサと広げ、雨を払っていた。
休み時間はとっくに終わっている。
次は数学の時間だから、適当に言い訳していけばいいだろ。
そう思う僕の頭の中からは、だんだんと傘の映像が薄れていく。
φ
それでも、家に帰る度、雨の日にそれを手にする度に、その日の出来事は何度もフラッシュバックしていた。
ただ、それはもうどこか現実味がない映像になっていて・・・。
彼女のことを想像する度に湧き上がる淡い炭酸水のような、そんなどこか甘酸っぱくも痛い気持ち。
しぼんでは膨らむその気持ちは、やっぱりこの傘のようで、僕は思わず傘の柄をぐっと握り締めた。
通り過ぎる車が時折あげる水しぶきを何度も避けながら、僕は目的地に辿り付く。
目の前に見えてくるいつものコンビニを見て、僕は一度傘をくるりと回した。
まだ、彼女がいない時間帯だった気がするし、多分大丈夫。
音を立てないようにそっと傘立てに近付き、くるくるとまわしながら傘を回す。
そして、傘を立て掛け、何食わぬ顔をして僕はコンビニに入った。
「いらっしゃいませー」
−ツバキちゃんの声だった。
僕は思わず舌打ちをして、雑誌コーナーへとターンする。
チラチラとレジを伺っていると、やがて彼女は店の奥へと声をかけ、エプロンを外し始めた。
どうやら交代の時間みたいだ。
ひょっとしたら傘に気付くかもしれない、そう思えば思うほど、しなくてもいいはずの緊張が妙に高まってきた。
「店長、お先に失礼しまーす」
入口付近で柔らかいメゾソプラノの声が響いたかと思うと、次の瞬間、
「あれ、この傘・・・」
そういいながら彼女は傘を手にする。
−やっぱりツバキちゃんのだよな・・・。
なぜか湧き上がるうれしい気持ちと、さみしい気持ち。
そして、色を濃くする罪悪感。
「わたしが探してた傘ありましたよー!よかった・・・」
「おお、あの傘か。よかったね、ツバキちゃん」
そんな会話を聞きながら、コンビニを出ようと雑誌を元の棚に戻した時、客が一人入ってきた。
メットをかぶった若い男の人だ。
「・・・あれ、タロウくん、何してるの?」
「へへ、迎えにきちゃった」
タロウくんと呼ばれたその男は、メットを脱ぎ、彼女の傘を手に取った。
「ん?ツバキこの傘って・・・」
「うん、今見つかったの。誰かが間違えて持ってったのを返してくれたんだと思う。
ほら、タロウくんのサインも入ってるし」
え・・・と呆気に取られている僕を尻目に、その男は傘をくるくると回しながら、
「お前に貸すとロクなもんじゃないよな・・・って時間ないし、そろそろ行くか」
と彼女を促し、店を出て行った。
φ
あれから数年が過ぎ・・・。
そんな苦い想いが一杯だった雨も、今ではそんなに気にならなくなった。
キライだった雨。
そして、やがてせつなさを増した雨。
それも、自分なりの防御壁になるんだとわかった今では、いい思い出って言えるようになったんだろうか。
ドアを締めながら、僕は傘を開く。
「ツバキ、そろそろ時間が・・・」
「あ、トーマくん、ちょっと待ってくれる?あなたの旅行券がまだテーブルに置いてあるわよ」
そんな彼女の言葉に、僕は慌てて傘を投げ出し、家の中に舞い戻る。
投げ出された傘の裏には、掠れた文字でTのイニシャルが僅かに残っていた。
PR
| 2004 |
| 07,07 |
«アマノガワ»
一年に一度、とある男女が逢瀬を楽しむ日。
そう聞くとどこか生々しいトーンなのに、なぜかすごく透明感のある光景が浮かぶ。
わたしにとっての七夕は、いつだってそうだった。
小学生の頃から出入りしていたプラネタリウム。
叔父がここの館長をしていたこともあって、わたしはここで幾度も無表情の空を眺めてきた。
何も見えないスクリーンが漆黒の闇を映し、そこに光を称えるとき、わたしはその美しさと、どこか虚無感漂う空間に酔う。
家庭の事情から、父親とも母親とも引き離されて育ったわたしにとって、親代わりの叔父から与えてもらったのは、自分の心のように早変わりしていくこの空模様だったのかもしれない。
その中でもスキだったのは、七夕の夜だった。
その昔、七夕の夜には、叔父の解説付のプラネタリウムのスペシャルプログラムを堪能した後、一年に2回だけ、両親とディナーを共にするのが定例となっていた。
一年に一度、男女がめぐり合う。
何も知らないわたしに取って、それは他ならぬ大好きだった両親との再会のイメージだったんだ。
「ユキちゃん、そろそろ準備はできた?」
「あ、はい、大丈夫です。清掃も済んでます」
頭上から降ってくる叔父の声に、わたしは慌てて声を張り上げた。
感傷的な想いを慌てて振り払い、階段状になった観客席を駆け上がる。
−考えてはいけない。そう、もう忘れるって決めたじゃない。
浮かぶ苦笑いは、きっと心をだまそうとしている証拠。
忘れるって決めたということは、まだ忘れられないということなんだろう。
17歳になって、両親とのディナーももはや過去のものとなり・・・わたしは、こうして七夕の夜はプラネタリウムの一アルバイトとして過ごす。
せめて、その透明なイメージと。。。泣きたくなるような気持ちを空に送るために。
ブーッ。
けたたましいブザーの音。
以前よりもずいぶんと少なくなったけれど、それでもこの日の夜には多くの人がここにやってくる。
やがて、煌々とした明かりがトーンを落とし、代わって闇の気配が忍び寄ってくる。
このプラネタリウムは、もう随分設備も古くなったと聞くけれど、それでもこの星が瞬き始める瞬間の光景というのは、思わず息を呑むほどだ。
観客の誘導を終えたわたしは、ドアにもたれ掛かりながら、ぼんやりとその光景を眺めていた。
そして−。
「ようこそ、プラネタリウム『アルデバラン』へ。
今宵は、特別プログラムとして、織姫と彦星の逢瀬の物語を、この星を使いながら楽しんでいただきましょう」
太いバリトンの声の持ち主は、叔父のものだ。
こうやって、特別な夜には、自らマイクを持って話すのが、創造性豊かな叔父らしい。
いつもと違い、BGMもピアノトリオのジャズのCDを掛けながら、なんともムーディーな雰囲気がドーム一帯に広がる。
15分ほど、プログラムを楽しんでいると、ふと気になる光景が映った。
わたしのすぐ右、席でいう最後尾の右側に座っている男の子がいたんだ。
ちょっと可愛らしい顔立ちで、クセのないストレートな髪。
おそらくわたしと同じくらいの年かしら?
まだ随分と顔立ちは幼く見えるけれど、意思の強さが現れている顔にわたしは思わず見入ってしまった。
でも、その彼は、人目もはばからず、ポロポロと泣いていた。
上を向きながら泣いているから、白いハーフジップのパーカーが涙で濡れていくのが暗い中でもわかる。
なんだか、そんな彼の表情を見ていると、わたしの方まで思い出してはいけない感情を呼び起こしてしまいそうだった。
3年前の七夕の日。
もう、両親と3人で食事をするなんて幻想が、壊れてしまった日。
進むべき道があって、それに迷うなんて、どれほどうらやましかったことだろう。
わたしにとって、自分の道を見つけるというのは、途方もなく困難なことだった。
それを示してくれるのは、星だけなのかもしれない、そう思っていたくらいだから。
14歳のわたしが、人工の空の下で泣きじゃくっていた、あの顔と思わずダブってしまって、わたしまで感傷的な想いに囚われる。
−宙(そら)は人の想いを映すんだ。
そう言ってくれたのは、あのとき泣きじゃくってるわたしを見た叔父の言葉だった。
結局、彼は上映が終わり、ドームが明るくなっても、相変わらず席に座ったままだった。
彼以外のお客様が帰り、わたしも清掃をはじめる。
置き去りにされたペットボトルをそっと摘み上げ、不審物だけチェックし、彼がいる周りの席以外は掃除を終えたわたしは、
「あの・・・お客様?」と声をかけた。
彼は、はっと我に返った様子で、慌てて真っ赤になった眼を擦り、
「あ、えと・・・すみません」と申し訳なさそうな表情で席を立ち、そのまま走って行ってしまった。
バタンと音を立ててドアが閉まる音をわたしもぼんやりと聞いていたような気がする。
「彼はね、有名な医者の息子なんだよ」
いきなり響くバリトンに思わず振り向くと、随分と楽な格好の叔父の姿があった。
「あら、お疲れ様です、叔父さん」
「こら、館長と呼ばんか、ここでは」と苦笑交じりの叔父は、短くそろえられた顎鬚をいじりながら、ふと空を見上げた。
何もない空。
さっきまで二つの星が逢瀬を重ねていた空だ。
「あの子は、君と違ってね、道を強いられているあまりに、現実と希望との軋轢で苦しんでるんだ。
道を決められるというのは、楽だけど、それに抗うのは、道なき道を行くよりも大変なのかもしれないね」
「わたしは・・・よくわからない。けど、叔父さん、前言ってたよね?
宙は人の思いを映すんだ、って。あの子が見ている空は、押しつぶされそうなくらいに重たくて、でもすごくキレイだったの」
そんな一方的な出会いから、わたしが彼と出会うのは、さらに数年後のお話。
透明な想いは、今ではもうすっかり様々な色に染まっているけれど、あのときの空の色は今でもあの天の川の片隅に残っている。
そう聞くとどこか生々しいトーンなのに、なぜかすごく透明感のある光景が浮かぶ。
わたしにとっての七夕は、いつだってそうだった。
小学生の頃から出入りしていたプラネタリウム。
叔父がここの館長をしていたこともあって、わたしはここで幾度も無表情の空を眺めてきた。
何も見えないスクリーンが漆黒の闇を映し、そこに光を称えるとき、わたしはその美しさと、どこか虚無感漂う空間に酔う。
家庭の事情から、父親とも母親とも引き離されて育ったわたしにとって、親代わりの叔父から与えてもらったのは、自分の心のように早変わりしていくこの空模様だったのかもしれない。
その中でもスキだったのは、七夕の夜だった。
その昔、七夕の夜には、叔父の解説付のプラネタリウムのスペシャルプログラムを堪能した後、一年に2回だけ、両親とディナーを共にするのが定例となっていた。
一年に一度、男女がめぐり合う。
何も知らないわたしに取って、それは他ならぬ大好きだった両親との再会のイメージだったんだ。
「ユキちゃん、そろそろ準備はできた?」
「あ、はい、大丈夫です。清掃も済んでます」
頭上から降ってくる叔父の声に、わたしは慌てて声を張り上げた。
感傷的な想いを慌てて振り払い、階段状になった観客席を駆け上がる。
−考えてはいけない。そう、もう忘れるって決めたじゃない。
浮かぶ苦笑いは、きっと心をだまそうとしている証拠。
忘れるって決めたということは、まだ忘れられないということなんだろう。
17歳になって、両親とのディナーももはや過去のものとなり・・・わたしは、こうして七夕の夜はプラネタリウムの一アルバイトとして過ごす。
せめて、その透明なイメージと。。。泣きたくなるような気持ちを空に送るために。
ブーッ。
けたたましいブザーの音。
以前よりもずいぶんと少なくなったけれど、それでもこの日の夜には多くの人がここにやってくる。
やがて、煌々とした明かりがトーンを落とし、代わって闇の気配が忍び寄ってくる。
このプラネタリウムは、もう随分設備も古くなったと聞くけれど、それでもこの星が瞬き始める瞬間の光景というのは、思わず息を呑むほどだ。
観客の誘導を終えたわたしは、ドアにもたれ掛かりながら、ぼんやりとその光景を眺めていた。
そして−。
「ようこそ、プラネタリウム『アルデバラン』へ。
今宵は、特別プログラムとして、織姫と彦星の逢瀬の物語を、この星を使いながら楽しんでいただきましょう」
太いバリトンの声の持ち主は、叔父のものだ。
こうやって、特別な夜には、自らマイクを持って話すのが、創造性豊かな叔父らしい。
いつもと違い、BGMもピアノトリオのジャズのCDを掛けながら、なんともムーディーな雰囲気がドーム一帯に広がる。
15分ほど、プログラムを楽しんでいると、ふと気になる光景が映った。
わたしのすぐ右、席でいう最後尾の右側に座っている男の子がいたんだ。
ちょっと可愛らしい顔立ちで、クセのないストレートな髪。
おそらくわたしと同じくらいの年かしら?
まだ随分と顔立ちは幼く見えるけれど、意思の強さが現れている顔にわたしは思わず見入ってしまった。
でも、その彼は、人目もはばからず、ポロポロと泣いていた。
上を向きながら泣いているから、白いハーフジップのパーカーが涙で濡れていくのが暗い中でもわかる。
なんだか、そんな彼の表情を見ていると、わたしの方まで思い出してはいけない感情を呼び起こしてしまいそうだった。
3年前の七夕の日。
もう、両親と3人で食事をするなんて幻想が、壊れてしまった日。
進むべき道があって、それに迷うなんて、どれほどうらやましかったことだろう。
わたしにとって、自分の道を見つけるというのは、途方もなく困難なことだった。
それを示してくれるのは、星だけなのかもしれない、そう思っていたくらいだから。
14歳のわたしが、人工の空の下で泣きじゃくっていた、あの顔と思わずダブってしまって、わたしまで感傷的な想いに囚われる。
−宙(そら)は人の想いを映すんだ。
そう言ってくれたのは、あのとき泣きじゃくってるわたしを見た叔父の言葉だった。
結局、彼は上映が終わり、ドームが明るくなっても、相変わらず席に座ったままだった。
彼以外のお客様が帰り、わたしも清掃をはじめる。
置き去りにされたペットボトルをそっと摘み上げ、不審物だけチェックし、彼がいる周りの席以外は掃除を終えたわたしは、
「あの・・・お客様?」と声をかけた。
彼は、はっと我に返った様子で、慌てて真っ赤になった眼を擦り、
「あ、えと・・・すみません」と申し訳なさそうな表情で席を立ち、そのまま走って行ってしまった。
バタンと音を立ててドアが閉まる音をわたしもぼんやりと聞いていたような気がする。
「彼はね、有名な医者の息子なんだよ」
いきなり響くバリトンに思わず振り向くと、随分と楽な格好の叔父の姿があった。
「あら、お疲れ様です、叔父さん」
「こら、館長と呼ばんか、ここでは」と苦笑交じりの叔父は、短くそろえられた顎鬚をいじりながら、ふと空を見上げた。
何もない空。
さっきまで二つの星が逢瀬を重ねていた空だ。
「あの子は、君と違ってね、道を強いられているあまりに、現実と希望との軋轢で苦しんでるんだ。
道を決められるというのは、楽だけど、それに抗うのは、道なき道を行くよりも大変なのかもしれないね」
「わたしは・・・よくわからない。けど、叔父さん、前言ってたよね?
宙は人の思いを映すんだ、って。あの子が見ている空は、押しつぶされそうなくらいに重たくて、でもすごくキレイだったの」
そんな一方的な出会いから、わたしが彼と出会うのは、さらに数年後のお話。
透明な想いは、今ではもうすっかり様々な色に染まっているけれど、あのときの空の色は今でもあの天の川の片隅に残っている。
| 2004 |
| 06,12 |
«月への階段»
満月の夜は、宙(そら)を見に行く。
布団をそっと抜け出し、寝ているモグを起こさないように、そっと服の袖に手を通す。
グローブをギュッと締めながら、ドアノブに手をかけると、
「ご主人様。。。黙って行くのはダメクポ」
ドキッとして思わず振り向くと、パッチリと目を見開いたモグが申し訳なさそうな顔で僕を見ていた。
「ちょっと散歩してくるから、寝てていいよ。疲れてるだろ?」
「でも・・・」
「多分朝日が出るまでには帰るよ。オレのことなら心配しないでいいからさ」
そう言いながらモグハウスの扉を開くと、一気に外の冷気が押し寄せてくる。
ちょっと軽装備すぎたかな、と思いながらも後ろ手にドアを押しやった。
「…あったかいスープを用意してるから、早く帰ってくるクポよ…」
ドア越しに聞こえるモグの声は、どこか困ったような、でもそのスープのようにすごく温かい声だったんだ。
冬のロンフォールは、冷気のせいか、真っ白な霧に包まれ、まるで緑と白のグラデーションの中に自分が溶けていくような気がする。
月明かりがかすかに先を照らす中、僕は白い息を吐きながら、少し早足で目的地へと急いだ。
サンドリアの街からバグパイプの音色が、どんどん遠ざかっていく。
やがて霧の森を抜ける頃、ふと道を外れたところに、崩れた煉瓦の山が見えてきた。
僕は煉瓦の側に腰を下ろし、懐からひとつ、崩れかけた煉瓦を取り出す。
ふぅっと手にした煉瓦に白い息を飛ばすと、煉瓦から赤いクリスタルの欠片が微かに舞い、やがて霧の中へと消えていった。
手の煉瓦を山の中へと加え、僕は地面へと寝転がった。
冬の冷気が冷たくも心地よくて、僕はふとまどろみながら、真上に見える緑の月を目に焼き付ける。
もうこうやって宙を、月を見に来るようになって、2年が経つ。
そのたびに、何度だって胸に問い掛けることがあるんだ。
−僕はちゃんと歩めてるかな?君と約束した、月への階段を。
布団をそっと抜け出し、寝ているモグを起こさないように、そっと服の袖に手を通す。
グローブをギュッと締めながら、ドアノブに手をかけると、
「ご主人様。。。黙って行くのはダメクポ」
ドキッとして思わず振り向くと、パッチリと目を見開いたモグが申し訳なさそうな顔で僕を見ていた。
「ちょっと散歩してくるから、寝てていいよ。疲れてるだろ?」
「でも・・・」
「多分朝日が出るまでには帰るよ。オレのことなら心配しないでいいからさ」
そう言いながらモグハウスの扉を開くと、一気に外の冷気が押し寄せてくる。
ちょっと軽装備すぎたかな、と思いながらも後ろ手にドアを押しやった。
「…あったかいスープを用意してるから、早く帰ってくるクポよ…」
ドア越しに聞こえるモグの声は、どこか困ったような、でもそのスープのようにすごく温かい声だったんだ。
冬のロンフォールは、冷気のせいか、真っ白な霧に包まれ、まるで緑と白のグラデーションの中に自分が溶けていくような気がする。
月明かりがかすかに先を照らす中、僕は白い息を吐きながら、少し早足で目的地へと急いだ。
サンドリアの街からバグパイプの音色が、どんどん遠ざかっていく。
やがて霧の森を抜ける頃、ふと道を外れたところに、崩れた煉瓦の山が見えてきた。
僕は煉瓦の側に腰を下ろし、懐からひとつ、崩れかけた煉瓦を取り出す。
ふぅっと手にした煉瓦に白い息を飛ばすと、煉瓦から赤いクリスタルの欠片が微かに舞い、やがて霧の中へと消えていった。
手の煉瓦を山の中へと加え、僕は地面へと寝転がった。
冬の冷気が冷たくも心地よくて、僕はふとまどろみながら、真上に見える緑の月を目に焼き付ける。
もうこうやって宙を、月を見に来るようになって、2年が経つ。
そのたびに、何度だって胸に問い掛けることがあるんだ。
−僕はちゃんと歩めてるかな?君と約束した、月への階段を。
| 2004 |
| 05,13 |
人が行き交う週末の夜。
湿気のない乾いた暖かさを纏った空気が、一帯に広がって、ちょっぴりヒュプノスの神を起こしてしまいそうな、そんな春の夜。
子供の頃、初めて買ってもらったフルートのように、透き通ったシルバーの月が、目の前に大きくぶら下がっているのが映る。
車道の前で手を上げると、そこに一台のタクシーが滑り込んできた。
「どちらまで行かれます?」
「ちょっとそこまで」
僕が答えると、頭に白いものが混じる堅実そうな運転手は、顔を顰め、怪訝そうな顔で僕を見やった。
軽く咳払いし、僕はもう一度言い直す。
「あそこに見える月まで」
車は滑らかに、推進力を上げて、ふわりと風に乗った。
アルデバランの赤い星を斜め下に見ながら、タクシーは斜度を上げて浮かんでいく。
「月に何しにいくんだい?兄ちゃん」
「ちょっと、人に会いに行くんだ」
「ほー、カノジョさんかい?」
如何にも堅物そうな印象の運転手の声のトーンがちょっぴり柔らかくなる。
硬質のバイオリンからチェロへの変化くらい、微妙な変化ではあったのだけど。
やがて、タクシーは止まり、静かの海の真中で僕は降りた。
地上へと走り去るタクシーのテールランプが赤く2回点滅し、やがて真っ黒な宙の彼方へと吸い込まれていく。
瞼を閉じた。
その裏に浮かぶいくつもの情景。
走り去って、やがて収斂していく距離。
ふと目を開けたときには、君が横にいたんだ。
静かの海の真中で、少しウェーブした髪を払い、ゆったりとしたドレスの裾を引き摺って、僕の手を握る。
なんて穏やかな時間なんだろう。
こんなに満ち足りて、温かな時間があるなんて、思ったこともなかったんだ。
子供の頃、カゼで寝込んでる時にお袋が作ってくれたホットミルクみたいだ、とちょっと思い出して僕は一人でクスクスと笑う。
そんな僕を見て、柔らかな笑顔を見せる君と、一緒に並んで腰を下ろした。
時に制限のない状態でふらりと宙に浮かんでるような、そんな感覚に僕はしばし酔った。
「…さん?」
誰かが僕を揺り動かしている。
このまま目覚めなければいいのに、と思いつつ、目を擦りながらぼやけた視界の向こうに見えてきたのは、タクシーの運転手の顔だった。
「もう着きましたよ」
目を開けると、そこは見慣れたマンションの前。
一万円札を手渡しながら、お釣りを数えている運転手を横目に見やりながら、僕は窓の外へと目を向けた。
4階の一番左の部屋はもう灯りが煌々と点っている。
タクシーから降りると、少しだけ風が冷たかった。
まだ夏までは遠い、か。。。
そんなことを思いながら、疲れている彼女を気にして、僕はインターフォンを押さずに、カバンの中から猫のホルダーのついたカギを取り出す。
冷たく差し込む風に首を竦めながらマンションのオートロックに鍵を差し込んでいると、運転手がドアを閉めながらこう呟いたんだ。
「…月までの料金は特別に無料にしておくよ、兄ちゃん」
思わず振り返ったとき、そこにはタクシーの影も形もなかった。
なんだか妙におかしくなって僕はガラス扉の向こうに見える銀色の月を見ながら、ちょっとだけ笑った。
−風の前の塵に同じ、かあ。
後ろで扉が閉まる音を聞きながら、僕は彼女のいる月へと急ぐ。
エレベーターで10秒と少しの君の月へ。
湿気のない乾いた暖かさを纏った空気が、一帯に広がって、ちょっぴりヒュプノスの神を起こしてしまいそうな、そんな春の夜。
子供の頃、初めて買ってもらったフルートのように、透き通ったシルバーの月が、目の前に大きくぶら下がっているのが映る。
車道の前で手を上げると、そこに一台のタクシーが滑り込んできた。
「どちらまで行かれます?」
「ちょっとそこまで」
僕が答えると、頭に白いものが混じる堅実そうな運転手は、顔を顰め、怪訝そうな顔で僕を見やった。
軽く咳払いし、僕はもう一度言い直す。
「あそこに見える月まで」
車は滑らかに、推進力を上げて、ふわりと風に乗った。
アルデバランの赤い星を斜め下に見ながら、タクシーは斜度を上げて浮かんでいく。
「月に何しにいくんだい?兄ちゃん」
「ちょっと、人に会いに行くんだ」
「ほー、カノジョさんかい?」
如何にも堅物そうな印象の運転手の声のトーンがちょっぴり柔らかくなる。
硬質のバイオリンからチェロへの変化くらい、微妙な変化ではあったのだけど。
やがて、タクシーは止まり、静かの海の真中で僕は降りた。
地上へと走り去るタクシーのテールランプが赤く2回点滅し、やがて真っ黒な宙の彼方へと吸い込まれていく。
瞼を閉じた。
その裏に浮かぶいくつもの情景。
走り去って、やがて収斂していく距離。
ふと目を開けたときには、君が横にいたんだ。
静かの海の真中で、少しウェーブした髪を払い、ゆったりとしたドレスの裾を引き摺って、僕の手を握る。
なんて穏やかな時間なんだろう。
こんなに満ち足りて、温かな時間があるなんて、思ったこともなかったんだ。
子供の頃、カゼで寝込んでる時にお袋が作ってくれたホットミルクみたいだ、とちょっと思い出して僕は一人でクスクスと笑う。
そんな僕を見て、柔らかな笑顔を見せる君と、一緒に並んで腰を下ろした。
時に制限のない状態でふらりと宙に浮かんでるような、そんな感覚に僕はしばし酔った。
「…さん?」
誰かが僕を揺り動かしている。
このまま目覚めなければいいのに、と思いつつ、目を擦りながらぼやけた視界の向こうに見えてきたのは、タクシーの運転手の顔だった。
「もう着きましたよ」
目を開けると、そこは見慣れたマンションの前。
一万円札を手渡しながら、お釣りを数えている運転手を横目に見やりながら、僕は窓の外へと目を向けた。
4階の一番左の部屋はもう灯りが煌々と点っている。
タクシーから降りると、少しだけ風が冷たかった。
まだ夏までは遠い、か。。。
そんなことを思いながら、疲れている彼女を気にして、僕はインターフォンを押さずに、カバンの中から猫のホルダーのついたカギを取り出す。
冷たく差し込む風に首を竦めながらマンションのオートロックに鍵を差し込んでいると、運転手がドアを閉めながらこう呟いたんだ。
「…月までの料金は特別に無料にしておくよ、兄ちゃん」
思わず振り返ったとき、そこにはタクシーの影も形もなかった。
なんだか妙におかしくなって僕はガラス扉の向こうに見える銀色の月を見ながら、ちょっとだけ笑った。
−風の前の塵に同じ、かあ。
後ろで扉が閉まる音を聞きながら、僕は彼女のいる月へと急ぐ。
エレベーターで10秒と少しの君の月へ。
| 2004 |
| 03,18 |
東の空を見上げると、青く透き通った真珠のような星が見える。
−スピカだ。
この星が見えると、そろそろこの街にも春がやって来る。
こうやって星を見ていると、つい心が無防備になってしまって、思わず涙がこぼれそうになって、慌てて真上を向いて、涙を乾かすんだ。
もう成人したというのに、俺はそうやって自分の涙を誤魔化しながら今日まで歩いてきた。
「…スピカ?ね、そうだよね?」
ケバケバしい女の声に思わず振り向くと、中学の同級生だったトゥルが目を見開いて立ちすくんでいた。
「トゥル。。。もう5年ぶりだっけ?元気してっか?」
「あたりきしゃりき。…あんた、なんか垢抜けたねー。スピカって感じじゃないみたい」
「そういうおまえだって。…アークトゥルスって感じじゃないよな、もう」
俺はコートのポケットの奥に入り込んだ煙草の箱を弄りながら、そっとトゥルの顔を盗み見た。
−すっかり女の顔になったな、こいつ。
ちょっと口惜しいような、でもどこか眩しいような、そんな言葉にならない気持ちを持て余してる自分に気が付いて、俺はぎゅっと煙草の箱を握りつぶす。
そっと心から忍び寄ってきた忘れかけていた、それでいて新しく生まれた名もなき感情に背を向けたくて、思わずきゅっと目を瞑った。
スピカ、それは俺の中学のときの名前だった。
誰も本名なんか覚えちゃいない。
髪の毛も長く、成長期の女の子よりずっと女の子らしいと評されたあの頃の自分。
入学して以来、3年間ずっと俺はその名前でしか呼ばれることはなかった。
そんな俺にちょっかいを出してきた女がアークトゥルス、通称トゥルだ。
おとめ座のスピカに対し、オレンジに輝く男性的なうしつかい座の星、アークトゥルスは、春の夫婦星と準えることが多い。
女子からのバレンタインで靴箱が溢れ返るくらいの伝説を作ったトゥルは、アークトゥルスになぞらえるように、当時は奔放で男らしい性格で、いつも白い歯を見せて大口開けて笑っていた。
なにかと俺にちょっかいを出すんだけど、実際は俺のほうが奔放な彼女を放っておけなくて、世話女房みたいになってたのが他のヤツらには、スピカとアークトゥルスみたいに見えたんだろうな。
アークトゥルスがだんだん縮まってトゥルになり、、、俺達は3年間、夫婦星のように連れ添って歩いていた。
もっとも、スキとか嫌いなんて感情もよくわからなかった頃だ。
結局、周りの冷やかし以上の仲に進展することもなく、やがて卒業後は連絡も取らなくなり。
そうしていつしか5年の年月が経ったというわけだった。
5年の間に、俺は当時150cmもなかった身長が175cmに伸びた。
中学時代のようにスピカって名前で呼ばれることももうなくなって久しい。
トゥルは、身長は当時と同じくらいだから、多分170cmくらいだろう。
でも、纏っている空気が、女でないと出せないそれだったからか、隣にいると思わず甘酸っぱい衝動に駆られてしまいそうで、俺は何度も首を振ってそれを否定した。
「スピカさ、なんであんたスピカって呼ばれてたか知ってる?」
「え?そりゃ俺が小さくて女みたいだったからだろ」
そう答えると、彼女は含み笑いをしながら、コホンと咳払いを一つ。
「スピカはね、アラビア語でアルシマクアルアザルって言うんだけどさ」
「アルシ…なんだって?」
「日本語でいうと無防備状態。当時のあんたって、針剥き出しにして歩いてるような感じだったもの。だからスピカ」
なるほどな、と思った。
スピカのSpicというのは、確か針とかとがったもの、なんて意味があったような気がする。
スパイクなんかの語源にもなってる言葉のはずで、そんな無防備に針を曝け出してるようなヤツだからスピカと呼ばれてた、ということらしい。
ふと時計を見ると21時だった。
「…なあ、今から何か予定あるのか?」
「ん?一応」
「そっか。…んじゃいいや。またな」
自分でも不自然だと思いながらトゥルに背を向けて手を上げる。
何を俺は今言おうとしたんだろう。
女を見るとすぐ腫れた惚れただ、となっちまうのも中学生のガキみたいで嫌になったんだ。
頭上の青く透き通った星に舌打ちしながら歩き出したとき、
「…交換しよっか?」
トゥルの声が聞こえた。
「交換するって、なにを?」
「あたし達の名前」
驚いて振り向いた俺に、彼女は唇の端を上げて柔らかい笑みを見せて、こう言った。
「今日からはあんたがトゥルになるんだ。その代わり、あたしはスピカになるの」
結局、俺達は今度酒を飲み交わす約束をして別れた。
相変わらず色気もない約束だった。
「それじゃ、またな…スピカ」
「じゃあね」
呼びなれない、というよりも、本来自分がいつも心の奥で呼んできたもう一人の自分のようで、その名前を口にして思わず俺は俯いた。
でも、決して嫌な感情じゃなくて。
−こんなのも悪くないな。
再び彼女に背を向けて歩き出し、俺は空に向かって呟いた。
バイバイ、スピカ。
−スピカだ。
この星が見えると、そろそろこの街にも春がやって来る。
こうやって星を見ていると、つい心が無防備になってしまって、思わず涙がこぼれそうになって、慌てて真上を向いて、涙を乾かすんだ。
もう成人したというのに、俺はそうやって自分の涙を誤魔化しながら今日まで歩いてきた。
「…スピカ?ね、そうだよね?」
ケバケバしい女の声に思わず振り向くと、中学の同級生だったトゥルが目を見開いて立ちすくんでいた。
「トゥル。。。もう5年ぶりだっけ?元気してっか?」
「あたりきしゃりき。…あんた、なんか垢抜けたねー。スピカって感じじゃないみたい」
「そういうおまえだって。…アークトゥルスって感じじゃないよな、もう」
俺はコートのポケットの奥に入り込んだ煙草の箱を弄りながら、そっとトゥルの顔を盗み見た。
−すっかり女の顔になったな、こいつ。
ちょっと口惜しいような、でもどこか眩しいような、そんな言葉にならない気持ちを持て余してる自分に気が付いて、俺はぎゅっと煙草の箱を握りつぶす。
そっと心から忍び寄ってきた忘れかけていた、それでいて新しく生まれた名もなき感情に背を向けたくて、思わずきゅっと目を瞑った。
スピカ、それは俺の中学のときの名前だった。
誰も本名なんか覚えちゃいない。
髪の毛も長く、成長期の女の子よりずっと女の子らしいと評されたあの頃の自分。
入学して以来、3年間ずっと俺はその名前でしか呼ばれることはなかった。
そんな俺にちょっかいを出してきた女がアークトゥルス、通称トゥルだ。
おとめ座のスピカに対し、オレンジに輝く男性的なうしつかい座の星、アークトゥルスは、春の夫婦星と準えることが多い。
女子からのバレンタインで靴箱が溢れ返るくらいの伝説を作ったトゥルは、アークトゥルスになぞらえるように、当時は奔放で男らしい性格で、いつも白い歯を見せて大口開けて笑っていた。
なにかと俺にちょっかいを出すんだけど、実際は俺のほうが奔放な彼女を放っておけなくて、世話女房みたいになってたのが他のヤツらには、スピカとアークトゥルスみたいに見えたんだろうな。
アークトゥルスがだんだん縮まってトゥルになり、、、俺達は3年間、夫婦星のように連れ添って歩いていた。
もっとも、スキとか嫌いなんて感情もよくわからなかった頃だ。
結局、周りの冷やかし以上の仲に進展することもなく、やがて卒業後は連絡も取らなくなり。
そうしていつしか5年の年月が経ったというわけだった。
5年の間に、俺は当時150cmもなかった身長が175cmに伸びた。
中学時代のようにスピカって名前で呼ばれることももうなくなって久しい。
トゥルは、身長は当時と同じくらいだから、多分170cmくらいだろう。
でも、纏っている空気が、女でないと出せないそれだったからか、隣にいると思わず甘酸っぱい衝動に駆られてしまいそうで、俺は何度も首を振ってそれを否定した。
「スピカさ、なんであんたスピカって呼ばれてたか知ってる?」
「え?そりゃ俺が小さくて女みたいだったからだろ」
そう答えると、彼女は含み笑いをしながら、コホンと咳払いを一つ。
「スピカはね、アラビア語でアルシマクアルアザルって言うんだけどさ」
「アルシ…なんだって?」
「日本語でいうと無防備状態。当時のあんたって、針剥き出しにして歩いてるような感じだったもの。だからスピカ」
なるほどな、と思った。
スピカのSpicというのは、確か針とかとがったもの、なんて意味があったような気がする。
スパイクなんかの語源にもなってる言葉のはずで、そんな無防備に針を曝け出してるようなヤツだからスピカと呼ばれてた、ということらしい。
ふと時計を見ると21時だった。
「…なあ、今から何か予定あるのか?」
「ん?一応」
「そっか。…んじゃいいや。またな」
自分でも不自然だと思いながらトゥルに背を向けて手を上げる。
何を俺は今言おうとしたんだろう。
女を見るとすぐ腫れた惚れただ、となっちまうのも中学生のガキみたいで嫌になったんだ。
頭上の青く透き通った星に舌打ちしながら歩き出したとき、
「…交換しよっか?」
トゥルの声が聞こえた。
「交換するって、なにを?」
「あたし達の名前」
驚いて振り向いた俺に、彼女は唇の端を上げて柔らかい笑みを見せて、こう言った。
「今日からはあんたがトゥルになるんだ。その代わり、あたしはスピカになるの」
結局、俺達は今度酒を飲み交わす約束をして別れた。
相変わらず色気もない約束だった。
「それじゃ、またな…スピカ」
「じゃあね」
呼びなれない、というよりも、本来自分がいつも心の奥で呼んできたもう一人の自分のようで、その名前を口にして思わず俺は俯いた。
でも、決して嫌な感情じゃなくて。
−こんなのも悪くないな。
再び彼女に背を向けて歩き出し、俺は空に向かって呟いた。
バイバイ、スピカ。
カレンダー
プロフィール
カテゴリー
最新記事
(04/18)
(03/17)
(02/15)
(12/15)
(11/15)
最新TB
ブログ内検索