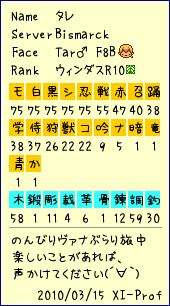| 2005 |
| 03,04 |
(先ほど#3をアップしましたので、先に#3からご覧ください)
#4 February 7,2005 Nagoya
数日後、会社を早退し、智也の通夜へと向かった。
新幹線で揺られる2時間ほどの間が、実は何よりも一番怖かった気がする。
それまでは、正直悲しみというよりはパニック状態だったけれど、最初の報せから時間が経ち、自分の中で冷静にそれを受け止められるに従い、どこか懐疑的なその事実を受け止める瞬間のことがイメージされて、思わず逃げ出したくなったんだろうか。
やがてまだ見ぬ駅が近づいてくるに従い、ここであいつが生きていたんだということを改めて感じ取った。
彼の母親に連絡をすると、「迎えを行かせます。バス停で待っててください」と言われ、ブツッと通話が途切れた。
程なくして、智也とそっくりの顔の高校生が姿を見せた。
ウルフベースのはねた髪や、ちょっと垂れた目、少しがっしりとした体つきなどから察すると、まずヤツの弟で間違いないかと思った。
向こうも気が付いたようで、「すみません、遠くから来ていただいて」と頭を下げられた。
俺も慌てて礼を返しながら、「智也の弟さんだよね?よく似てるなあ」と呟くと、ケイと名乗ったその弟は、「似て欲しくなかったんですけど、よく言われます」と言いながら笑った。
白い息を吐きながら歩くこと数分で、大きな葬儀会場に着いた。
もう通夜の時間は終わっていたようで、2階へと案内される。
そこには親類が集まっていて、代わる代わる火の番をしながら、故人との思い出を語り合ってる様子だったが、その割には雰囲気が明るいのが意外だった。
やがて、奥から明るい栗色のショートの女の人が出てきた。
すぐに、彼の母親だと分かったのだが、電話の声よりもすごく若い人だった。
「あら、アイツにイケメンの友達が」
と冗談を叩いて笑う母親に、何言ってるんスか、と軽くいなしながら、名前を告げると、少し驚いた様子で、彼女はこう告げた。
「そう、あなたが・・・。智也からよく話を聞いてたの。銀行員の友達がいるなんて珍しいなって」
「そうだったんですか・・・」
「憧れてるって言ってたよ」と彼女は笑いながら俺の肩をポンポンと叩いた。
−あれだけ憎まれ口を叩いていたのに、逝ってしまってからそういうこと言うなんてずるいよお前は。
そして、場の明るい雰囲気に俺は少し戸惑いを覚えていた。
もうこの場所では、あいつは「存在していない」のだろうか・・・。
複雑そうな俺の顔を見て、智也の母親は俺の手を引き、中へと案内してくれた。
そこには白い棺が置かれていた。
「よかったら手合わせてやってね」という彼女の声に、躓きかけていた勇気が少し舞い戻った。
恐る恐る中を覗き込む。
−やっぱり、中で目を閉じていたのは、俺のよく知っているあいつの姿だった。
そっと頬に触れてみた。
ヒンヤリというよりも、どこか重たくて、虚無感が圧し掛かってくるような、圧倒的な冷気が指の神経から脳へと伝わっていく。
智也の唇は、呼吸困難だったせいか、紫色に変色していて、どこか苦しげな表情が張り付いていた。
それを見た瞬間だった。
俺はこみ上げてくるものをこらえきれなくなった。
「この大バカ野郎・・・」
視界が涙で霞んで、ぬぐってもぬぐっても涙が止まらなかった。
それを見た彼の母親が、「ごめんねごめんね」と言いながら何度も頭をくしゃくしゃと撫でてくれて、それがまたすごく切なかった。
と、扉の辺りが俄かに騒がしくなり、やがて20歳前後と思しき男が3人くらい神妙な顔で入ってきた。
「あら、あんた達も来たの。ちょうどよかった、東京から智ちゃんのお友達がわざわざ来てくれたから紹介するわね」
と、俺のほうに話が飛んできたので、慌てて俺は頭を下げた。
どうやら、地元の幼馴染軍団のようだ。
とりあえずいったん扉の前で彼らの焼香を待って、辞去の挨拶だけしようと思ったところ、
「智と同い年くらいですか?」と彼らの中でも一番背の高い茶髪のサラサラ髪のヤツが声をかけてくる。
「いえ」と首を振り、20代の折り返しをまたいでいることを告げると、彼らは本当に驚いた様子で、しばらくその話でネタにされてしまった。
こういう時って、反応がしづらくて、居心地がよくないはずなのに・・・彼らとは、不思議と近いものを感じた。
互いに知らない智也の思い出を語ることができるからだろうか。
それとも、智也の大事な人たちとこんな形で出会ったから、何らかの痛みを覚えただろうか。
今は、まだその答えを出せそうになかった。
そのままおいとまする予定だったのだが、流れで彼の母親や幼馴染軍団と一緒に食事に行くことになった。
俺が彼ら幼馴染たちに不思議な近さを感じたのと同じく、彼らも俺に対して初対面とは思えないほど温かい接し方をしてくれたのがうれしかった。
もっとも、20前後のヤツらに「カワイイ」と表現されるのは断固抗議したいところだったのだが。
ようやく一息ついたファミレスで、俺は彼らと今回の事件について、互いの情報を交換する機会に恵まれた。
そして、そこで分かったのは、とても悲しい事実のみだった。
そう、俺が止めようにも、止めることが不可能だったことだけ。
智也は、不思議なことに携帯電話のメールや着信履歴をすべて残していた。
彼は、1月の下旬に、とあるメールを送っていた。
「サイトを見て興味を持った。仲間にしてほしい」
そして、そのメールの時刻には、俺は智也と一緒にメシを食っていたはずだった。
次のメールには、「今友達と一緒だから自殺のことバレるとやばい。また明日」というメールが書かれていて、それを裏付けることになる。
そして、その後の出来事を思い返していると、ふと大事なことを失念していることに気が付いた。
その二日後、俺は智也に呼び出され、ご飯を奢ってもらったのだった。
「なんだよ、珍しいな」といぶかしむ俺に対し、「いつも奢ってもらってるからさ、たまには」と笑いながら俺をうながし、好きなとこ連れてってやるよ、と彼なりの軽口にちょっとした違和感を覚えたのだが、結局はそのまま流してしまったような気がする。
ただ、その帰りに彼はiPodを購入していた。
U2のサインが入った限定モデルで、メタリックなデザインにクリムゾンレッドが映えるデザインで、何度も見せびらかしてきたのを思い出す。
そうやって、欲があるということは、言い換えれば希望が、そして夢があるということだ。
そんなヤツが軽々しく自殺するなんて、俺にはまだ信じられなかった。
結局、彼は誰にもそれを継げず、自殺志願者たちと共に、俺たちの手の届かない場所に行ってしまった。
彼の好きだったB'zの曲が流れるたびに、ふと頭を掠めるのは、だんだんとその事実に慣れていく自分が否定できないことなのかもしれない。
そうして「思い出す」ことで、俺はだんだんとその事実を受け入れ始めた。
そして、2週間が経ち−俺は彼の気配のない場所への引越し先を決めたのだった。
#Epilogue March 3,2005 Tokyo
春の気配が近づくはずの3月。
東京には季節外れの雪が降った。
俺は、およそ1ヶ月ぶりに目黒駅に立ち寄った。
特に感傷らしきものもなく、ただそこには智也がいないだけだった。
「どうしたの?キョロキョロしちゃって」
一緒に買い物に来ていた女友達が、俺の顔を覗き込んで不思議そうな目で見やった。
「なんでもない。とりあえずご飯でも食べに行こっか」
俺は笑いながらもう一度駅を振り返った。
智也のいない駅も、いつもの顔で人が行きかい、電車へと吸い込まれていく。
その光景は、俺にとって帰る場所ではなく、単に立ち寄るだけの場所にしか見えなかった。
結局、俺も彼も、「ただいま」と言える場所へと帰っていく、ただそれだけのことなのだろうか。
仕事、友達、趣味、好きな人、家族。
自分を構成するいくつものエレメントは、それぞれ自分を様々な形で高揚させつつも、結局はそれは自分を刺激するだけのもの。
俺がいつか帰るところは、きっと自分で「ただいま」と認められる場所でしかない。
自分にとって大事なものを得たり失ったりという過程の中で、自分が帰る場所の変遷はどう俺の中で息づいていくのだろう。
「何やってんの?早く行こうよ」
交差点の向こうから手を振る友達に手を振り返しながら、俺は白いものがちらつく外へと走り出した。
雪はだんだんと勢いと重さを増しながら、静かに地表へと舞い降りていく。
やがて駅は白い空気の中に静かに溶けて、人の波の中へと消えていった。
数日後、会社を早退し、智也の通夜へと向かった。
新幹線で揺られる2時間ほどの間が、実は何よりも一番怖かった気がする。
それまでは、正直悲しみというよりはパニック状態だったけれど、最初の報せから時間が経ち、自分の中で冷静にそれを受け止められるに従い、どこか懐疑的なその事実を受け止める瞬間のことがイメージされて、思わず逃げ出したくなったんだろうか。
やがてまだ見ぬ駅が近づいてくるに従い、ここであいつが生きていたんだということを改めて感じ取った。
彼の母親に連絡をすると、「迎えを行かせます。バス停で待っててください」と言われ、ブツッと通話が途切れた。
程なくして、智也とそっくりの顔の高校生が姿を見せた。
ウルフベースのはねた髪や、ちょっと垂れた目、少しがっしりとした体つきなどから察すると、まずヤツの弟で間違いないかと思った。
向こうも気が付いたようで、「すみません、遠くから来ていただいて」と頭を下げられた。
俺も慌てて礼を返しながら、「智也の弟さんだよね?よく似てるなあ」と呟くと、ケイと名乗ったその弟は、「似て欲しくなかったんですけど、よく言われます」と言いながら笑った。
白い息を吐きながら歩くこと数分で、大きな葬儀会場に着いた。
もう通夜の時間は終わっていたようで、2階へと案内される。
そこには親類が集まっていて、代わる代わる火の番をしながら、故人との思い出を語り合ってる様子だったが、その割には雰囲気が明るいのが意外だった。
やがて、奥から明るい栗色のショートの女の人が出てきた。
すぐに、彼の母親だと分かったのだが、電話の声よりもすごく若い人だった。
「あら、アイツにイケメンの友達が」
と冗談を叩いて笑う母親に、何言ってるんスか、と軽くいなしながら、名前を告げると、少し驚いた様子で、彼女はこう告げた。
「そう、あなたが・・・。智也からよく話を聞いてたの。銀行員の友達がいるなんて珍しいなって」
「そうだったんですか・・・」
「憧れてるって言ってたよ」と彼女は笑いながら俺の肩をポンポンと叩いた。
−あれだけ憎まれ口を叩いていたのに、逝ってしまってからそういうこと言うなんてずるいよお前は。
そして、場の明るい雰囲気に俺は少し戸惑いを覚えていた。
もうこの場所では、あいつは「存在していない」のだろうか・・・。
複雑そうな俺の顔を見て、智也の母親は俺の手を引き、中へと案内してくれた。
そこには白い棺が置かれていた。
「よかったら手合わせてやってね」という彼女の声に、躓きかけていた勇気が少し舞い戻った。
恐る恐る中を覗き込む。
−やっぱり、中で目を閉じていたのは、俺のよく知っているあいつの姿だった。
そっと頬に触れてみた。
ヒンヤリというよりも、どこか重たくて、虚無感が圧し掛かってくるような、圧倒的な冷気が指の神経から脳へと伝わっていく。
智也の唇は、呼吸困難だったせいか、紫色に変色していて、どこか苦しげな表情が張り付いていた。
それを見た瞬間だった。
俺はこみ上げてくるものをこらえきれなくなった。
「この大バカ野郎・・・」
視界が涙で霞んで、ぬぐってもぬぐっても涙が止まらなかった。
それを見た彼の母親が、「ごめんねごめんね」と言いながら何度も頭をくしゃくしゃと撫でてくれて、それがまたすごく切なかった。
と、扉の辺りが俄かに騒がしくなり、やがて20歳前後と思しき男が3人くらい神妙な顔で入ってきた。
「あら、あんた達も来たの。ちょうどよかった、東京から智ちゃんのお友達がわざわざ来てくれたから紹介するわね」
と、俺のほうに話が飛んできたので、慌てて俺は頭を下げた。
どうやら、地元の幼馴染軍団のようだ。
とりあえずいったん扉の前で彼らの焼香を待って、辞去の挨拶だけしようと思ったところ、
「智と同い年くらいですか?」と彼らの中でも一番背の高い茶髪のサラサラ髪のヤツが声をかけてくる。
「いえ」と首を振り、20代の折り返しをまたいでいることを告げると、彼らは本当に驚いた様子で、しばらくその話でネタにされてしまった。
こういう時って、反応がしづらくて、居心地がよくないはずなのに・・・彼らとは、不思議と近いものを感じた。
互いに知らない智也の思い出を語ることができるからだろうか。
それとも、智也の大事な人たちとこんな形で出会ったから、何らかの痛みを覚えただろうか。
今は、まだその答えを出せそうになかった。
そのままおいとまする予定だったのだが、流れで彼の母親や幼馴染軍団と一緒に食事に行くことになった。
俺が彼ら幼馴染たちに不思議な近さを感じたのと同じく、彼らも俺に対して初対面とは思えないほど温かい接し方をしてくれたのがうれしかった。
もっとも、20前後のヤツらに「カワイイ」と表現されるのは断固抗議したいところだったのだが。
ようやく一息ついたファミレスで、俺は彼らと今回の事件について、互いの情報を交換する機会に恵まれた。
そして、そこで分かったのは、とても悲しい事実のみだった。
そう、俺が止めようにも、止めることが不可能だったことだけ。
智也は、不思議なことに携帯電話のメールや着信履歴をすべて残していた。
彼は、1月の下旬に、とあるメールを送っていた。
「サイトを見て興味を持った。仲間にしてほしい」
そして、そのメールの時刻には、俺は智也と一緒にメシを食っていたはずだった。
次のメールには、「今友達と一緒だから自殺のことバレるとやばい。また明日」というメールが書かれていて、それを裏付けることになる。
そして、その後の出来事を思い返していると、ふと大事なことを失念していることに気が付いた。
その二日後、俺は智也に呼び出され、ご飯を奢ってもらったのだった。
「なんだよ、珍しいな」といぶかしむ俺に対し、「いつも奢ってもらってるからさ、たまには」と笑いながら俺をうながし、好きなとこ連れてってやるよ、と彼なりの軽口にちょっとした違和感を覚えたのだが、結局はそのまま流してしまったような気がする。
ただ、その帰りに彼はiPodを購入していた。
U2のサインが入った限定モデルで、メタリックなデザインにクリムゾンレッドが映えるデザインで、何度も見せびらかしてきたのを思い出す。
そうやって、欲があるということは、言い換えれば希望が、そして夢があるということだ。
そんなヤツが軽々しく自殺するなんて、俺にはまだ信じられなかった。
結局、彼は誰にもそれを継げず、自殺志願者たちと共に、俺たちの手の届かない場所に行ってしまった。
彼の好きだったB'zの曲が流れるたびに、ふと頭を掠めるのは、だんだんとその事実に慣れていく自分が否定できないことなのかもしれない。
そうして「思い出す」ことで、俺はだんだんとその事実を受け入れ始めた。
そして、2週間が経ち−俺は彼の気配のない場所への引越し先を決めたのだった。
春の気配が近づくはずの3月。
東京には季節外れの雪が降った。
俺は、およそ1ヶ月ぶりに目黒駅に立ち寄った。
特に感傷らしきものもなく、ただそこには智也がいないだけだった。
「どうしたの?キョロキョロしちゃって」
一緒に買い物に来ていた女友達が、俺の顔を覗き込んで不思議そうな目で見やった。
「なんでもない。とりあえずご飯でも食べに行こっか」
俺は笑いながらもう一度駅を振り返った。
智也のいない駅も、いつもの顔で人が行きかい、電車へと吸い込まれていく。
その光景は、俺にとって帰る場所ではなく、単に立ち寄るだけの場所にしか見えなかった。
結局、俺も彼も、「ただいま」と言える場所へと帰っていく、ただそれだけのことなのだろうか。
仕事、友達、趣味、好きな人、家族。
自分を構成するいくつものエレメントは、それぞれ自分を様々な形で高揚させつつも、結局はそれは自分を刺激するだけのもの。
俺がいつか帰るところは、きっと自分で「ただいま」と認められる場所でしかない。
自分にとって大事なものを得たり失ったりという過程の中で、自分が帰る場所の変遷はどう俺の中で息づいていくのだろう。
「何やってんの?早く行こうよ」
交差点の向こうから手を振る友達に手を振り返しながら、俺は白いものがちらつく外へと走り出した。
雪はだんだんと勢いと重さを増しながら、静かに地表へと舞い降りていく。
やがて駅は白い空気の中に静かに溶けて、人の波の中へと消えていった。
PR
| 2005 |
| 03,03 |
「冬は、空の色綺麗だな」
駅のホームに佇んでいる俺は、ふと懐かしい声を聞いた気がした。
辺りを見回しても誰もいない。
そして、俄かに一人苦笑した。
なぜなら、その言葉を俺に言った張本人は、同じ世界には存在していないから。
彼の言葉は、もう俺には届かなくなってしまった。
そんな俺が今、それに答えるならば言う言葉は決まっている。
−当たり前だろ。俺が生まれた季節なんだからさ。
「バカタレー。オレが生まれたからに決まってるだろ」
そう笑いながら憎まれ口を叩く彼の姿が目に浮かびそうで、視界がぼやけてきそうになる。
慌てて上を向くと、そこには本当に綺麗なスカイブルーが広がっていた。
青をどこまでも削り取ったようなその色は、彼の心情をどこか象徴してるような気がした。
#3 February 5,2005 Yokohama
2月5日。
そのときの俺は、同じように駅のホームに一人佇んでいた。
家探しのために渋谷の不動産屋と約束をしていたので、重い腰を上げて家から出たばかりだった。
雪が落ちてきそうなほどどんよりとした空だな、とぼんやりと思ったことがなぜか記憶の底に沈んでいる。
♪チャーラーラーラー
コートの中の携帯が大音量で鳴り出し、俺は慌ててポケットを弄った。
画面には、無二の親友の智也の名前が表示されていた。
ちょうど彼にも家探しのことを伝えようと思っていたところだったので、唇の端に笑みを浮かべながら、俺は通話ボタンを押した。
「はい、もしもしー」
「もしもしー。あの・・・」
びっくりしたことに、それは智也の声ではなく、大人びた女性の声だった。
その瞬間は、頭が混乱していて、自分がからかわれているような気がしたのだが、同時に何かがずっと頭の中で警鐘を鳴らしていた。
何かがおかしい。
「私、智也の母親です。息子がいつもお世話になりまして」
それを聞いて、余計に俺は迷宮へと迷い込んだ。
「は、はあ・・・」
そもそも、智也の家族とは一度も面識がなかったから、ただただ戸惑ってその声を聞き続けた。
突然の電話を詫びる彼の母親は、続けてその謎が氷解する言葉をつむいだ。
しかし、それは俺に取って、とても残酷な言葉だったのだ。
「ニュースをご覧になったとは思いますが・・・3日の午前中、亡くなりまして。
生前は、色々よくしていただいたそうで、ありがとうございました」
その言葉の意味が理解できるまで数秒の時間を要した。
「な・・・亡くなった?」
それから先のことはよく覚えていない。
彼の母親の声がひたすら受話器から流れ出していただけだった。
断片的に「自殺した」「メールの履歴から電話した」という言葉だけを耳の奥へと残して。
智也とは、不思議な出会い方をした。
美術系の専門学校に通っていた20歳の彼と、社会人の俺が接点を持つのは普通ならありえないことだ。
まして、親友になるとは全く思っていなかった。
1年以上前になるだろうか・・・彼の存在を知ったのは、オンラインゲーム上のことだ。
一緒にパーティーを組み、経験値を稼ぎに行っただけの仲。
戦闘中は全く無口だった彼が、何故パーティーが解散した後に俺に声をかけてきたのかは、今でも一番の謎だと思う。
というのも、俺がそのパーティーでは一番空回りしていたからだ。
他の人よりも3つほどレベルが低く、しかもアタッカーとしては不向きな種族を操っていて、今思い起こしても何故自分があのパーティーに誘われたのかよくわからない。
ただ、必死に迷惑をかけないようにとコントローラーを握り締めていた記憶だけがずっとこの手に残っている。
「今日は楽しかったよ。よかったらまた遊ぼう」
あいつの言葉が画面に現れたとき、本当に意外で、でもどこかその必死だった自分が救われたような気がして、すごくうれしかったんだ。
なのに、結局智也とそのゲームの中で遊んだ記憶はそれ以降ほとんどなかった。
勿論色々な話はしたのだが、結局ゲームの中での話より、今こんなことをしてる、こんなテレビやってる、なんて下世話な話から、将来の自分についてなんて青臭い話もたくさんした。
やがて、俺の実家が近いこともあって、一度会ってみたところ意気投合してしまい、それ以降は正直なところ、自分の彼女よりも多く時間を割いて彼と遊んでいたような気がする。
友達にもいろいろな友達がいるけれど、気軽に互いに呼びつけあい、軽口を叩いたり時に頭を叩いたりなんてコミュニケーションが取れるのは、本当に貴重だったのだ。
もっとも、その年齢に似合ってよく食べた彼の食事代も殆ど俺の財布から消えていたのだが、家族と離れて過ごす自分には、時に弟みたいな感じで接していたこともあって、あまりそういったことに対する不満は感じなかった。
−仕事であまり息を抜いて素の自分で話す機会が少なかったから。
素の自分で一番いられる瞬間があるのが何より大切だったから。
俺のほうが心のメリットをたくさんもらっていたからだなんて、あいつには結局伝えることができなかった。
1月に異動が出て都内に引っ越す旨を告げたとき、一番喜んだのが智也だった。
「いいから、うちの近くに引っ越してこいって。一緒に家探し付き合っちゃるから」
「ははーん。俺がいないと淋しいんだろ、テメーは」
「だって、近くに越してくれれば飯食いに行けるじゃん」
そう言いながらニタニタ笑うヤツの頭を2,3発叩いたのが昨日のことみたいだった。
2月いっぱい、課題の提出で忙しいという話をしていた彼の邪魔をしないように、とりあえずは彼の住む目黒の近くで、引越し候補先を決めておこうと思ったのが、そもそもの始まりだった。
それ以降も、iPodを買ったりしている姿も見ていたので、正直自殺という単語は彼にもっとも似つかわしくないように思えた。
だから・・・余計にショックだったのかもしれない。
彼が死んだことが、ではなくて。
それを気付いてあげたり、止めることができなかったことこそが、一番悔しくてならなかった。
ともあれ、不動産屋との約束の時間がそのときは迫っていた。
延期することも考えたのだが、何にせよ他にいけそうな日もなかったので、動揺しっぱなしの自分を留めて現地へと向かった。
結局、当初ネットで見かけた物件は、1月から女性専用になってたり、いいなと思った物件が宗教がらみだったりと、思った以上に物件探しは難航することになる。
「やっぱり目黒がいいですか?」
そう聞いてくる業者さんの顔に頷きかけた俺は、しばらくして首を横に振った。
「いや、やっぱりいいです。目黒の近くでいいんで、目黒を通らない場所にしてください」
事前に目黒周辺で、と伝えてたヤツが突然逆の希望を出したことに、少し不思議そうな顔をした業者さんは、
「・・・確かに、目黒周辺はいい物件すぐ出ちゃうからねぇ。ただ、もうちょっと待ってもらえればいい物件出せると思いますよ」
と俺に笑いかけた。その顔を直視できなかった俺は、目を伏せながら、こう呟いた。
「いや、もういいんです。ここに来るまでは拘ってたんだけど、その理由が無くなっちまったから」
その後、業者さんがどんな顔をしたのかは分からない。
結局、俺はそのまま席を立ったからだ。
7年ぶりの引越し。
それは、味わったのことのないほろ苦さを伴って始まったのだった。
駅のホームに佇んでいる俺は、ふと懐かしい声を聞いた気がした。
辺りを見回しても誰もいない。
そして、俄かに一人苦笑した。
なぜなら、その言葉を俺に言った張本人は、同じ世界には存在していないから。
彼の言葉は、もう俺には届かなくなってしまった。
そんな俺が今、それに答えるならば言う言葉は決まっている。
−当たり前だろ。俺が生まれた季節なんだからさ。
「バカタレー。オレが生まれたからに決まってるだろ」
そう笑いながら憎まれ口を叩く彼の姿が目に浮かびそうで、視界がぼやけてきそうになる。
慌てて上を向くと、そこには本当に綺麗なスカイブルーが広がっていた。
青をどこまでも削り取ったようなその色は、彼の心情をどこか象徴してるような気がした。
2月5日。
そのときの俺は、同じように駅のホームに一人佇んでいた。
家探しのために渋谷の不動産屋と約束をしていたので、重い腰を上げて家から出たばかりだった。
雪が落ちてきそうなほどどんよりとした空だな、とぼんやりと思ったことがなぜか記憶の底に沈んでいる。
♪チャーラーラーラー
コートの中の携帯が大音量で鳴り出し、俺は慌ててポケットを弄った。
画面には、無二の親友の智也の名前が表示されていた。
ちょうど彼にも家探しのことを伝えようと思っていたところだったので、唇の端に笑みを浮かべながら、俺は通話ボタンを押した。
「はい、もしもしー」
「もしもしー。あの・・・」
びっくりしたことに、それは智也の声ではなく、大人びた女性の声だった。
その瞬間は、頭が混乱していて、自分がからかわれているような気がしたのだが、同時に何かがずっと頭の中で警鐘を鳴らしていた。
何かがおかしい。
「私、智也の母親です。息子がいつもお世話になりまして」
それを聞いて、余計に俺は迷宮へと迷い込んだ。
「は、はあ・・・」
そもそも、智也の家族とは一度も面識がなかったから、ただただ戸惑ってその声を聞き続けた。
突然の電話を詫びる彼の母親は、続けてその謎が氷解する言葉をつむいだ。
しかし、それは俺に取って、とても残酷な言葉だったのだ。
「ニュースをご覧になったとは思いますが・・・3日の午前中、亡くなりまして。
生前は、色々よくしていただいたそうで、ありがとうございました」
その言葉の意味が理解できるまで数秒の時間を要した。
「な・・・亡くなった?」
それから先のことはよく覚えていない。
彼の母親の声がひたすら受話器から流れ出していただけだった。
断片的に「自殺した」「メールの履歴から電話した」という言葉だけを耳の奥へと残して。
智也とは、不思議な出会い方をした。
美術系の専門学校に通っていた20歳の彼と、社会人の俺が接点を持つのは普通ならありえないことだ。
まして、親友になるとは全く思っていなかった。
1年以上前になるだろうか・・・彼の存在を知ったのは、オンラインゲーム上のことだ。
一緒にパーティーを組み、経験値を稼ぎに行っただけの仲。
戦闘中は全く無口だった彼が、何故パーティーが解散した後に俺に声をかけてきたのかは、今でも一番の謎だと思う。
というのも、俺がそのパーティーでは一番空回りしていたからだ。
他の人よりも3つほどレベルが低く、しかもアタッカーとしては不向きな種族を操っていて、今思い起こしても何故自分があのパーティーに誘われたのかよくわからない。
ただ、必死に迷惑をかけないようにとコントローラーを握り締めていた記憶だけがずっとこの手に残っている。
「今日は楽しかったよ。よかったらまた遊ぼう」
あいつの言葉が画面に現れたとき、本当に意外で、でもどこかその必死だった自分が救われたような気がして、すごくうれしかったんだ。
なのに、結局智也とそのゲームの中で遊んだ記憶はそれ以降ほとんどなかった。
勿論色々な話はしたのだが、結局ゲームの中での話より、今こんなことをしてる、こんなテレビやってる、なんて下世話な話から、将来の自分についてなんて青臭い話もたくさんした。
やがて、俺の実家が近いこともあって、一度会ってみたところ意気投合してしまい、それ以降は正直なところ、自分の彼女よりも多く時間を割いて彼と遊んでいたような気がする。
友達にもいろいろな友達がいるけれど、気軽に互いに呼びつけあい、軽口を叩いたり時に頭を叩いたりなんてコミュニケーションが取れるのは、本当に貴重だったのだ。
もっとも、その年齢に似合ってよく食べた彼の食事代も殆ど俺の財布から消えていたのだが、家族と離れて過ごす自分には、時に弟みたいな感じで接していたこともあって、あまりそういったことに対する不満は感じなかった。
−仕事であまり息を抜いて素の自分で話す機会が少なかったから。
素の自分で一番いられる瞬間があるのが何より大切だったから。
俺のほうが心のメリットをたくさんもらっていたからだなんて、あいつには結局伝えることができなかった。
1月に異動が出て都内に引っ越す旨を告げたとき、一番喜んだのが智也だった。
「いいから、うちの近くに引っ越してこいって。一緒に家探し付き合っちゃるから」
「ははーん。俺がいないと淋しいんだろ、テメーは」
「だって、近くに越してくれれば飯食いに行けるじゃん」
そう言いながらニタニタ笑うヤツの頭を2,3発叩いたのが昨日のことみたいだった。
2月いっぱい、課題の提出で忙しいという話をしていた彼の邪魔をしないように、とりあえずは彼の住む目黒の近くで、引越し候補先を決めておこうと思ったのが、そもそもの始まりだった。
それ以降も、iPodを買ったりしている姿も見ていたので、正直自殺という単語は彼にもっとも似つかわしくないように思えた。
だから・・・余計にショックだったのかもしれない。
彼が死んだことが、ではなくて。
それを気付いてあげたり、止めることができなかったことこそが、一番悔しくてならなかった。
ともあれ、不動産屋との約束の時間がそのときは迫っていた。
延期することも考えたのだが、何にせよ他にいけそうな日もなかったので、動揺しっぱなしの自分を留めて現地へと向かった。
結局、当初ネットで見かけた物件は、1月から女性専用になってたり、いいなと思った物件が宗教がらみだったりと、思った以上に物件探しは難航することになる。
「やっぱり目黒がいいですか?」
そう聞いてくる業者さんの顔に頷きかけた俺は、しばらくして首を横に振った。
「いや、やっぱりいいです。目黒の近くでいいんで、目黒を通らない場所にしてください」
事前に目黒周辺で、と伝えてたヤツが突然逆の希望を出したことに、少し不思議そうな顔をした業者さんは、
「・・・確かに、目黒周辺はいい物件すぐ出ちゃうからねぇ。ただ、もうちょっと待ってもらえればいい物件出せると思いますよ」
と俺に笑いかけた。その顔を直視できなかった俺は、目を伏せながら、こう呟いた。
「いや、もういいんです。ここに来るまでは拘ってたんだけど、その理由が無くなっちまったから」
その後、業者さんがどんな顔をしたのかは分からない。
結局、俺はそのまま席を立ったからだ。
7年ぶりの引越し。
それは、味わったのことのないほろ苦さを伴って始まったのだった。
| 2005 |
| 02,25 |
「何時に来るのよ・・・全然来る気配ないんじゃないの?」
「う・・・おっかしいなあ。絶対この時間だっての」
俺は、不審そうにキョロキョロと首をまわす母親の頭を軽くはたいた。
勿論、2倍くらいになって返ってきた上に、元々無造作にワックスでいじってた髪が、半端じゃない無造作具合になったのは言うまでもない。
25日、引越し当日。
息子がまったく引越しの準備をしないことが不安になったのか、母親が昨夜から上京してきた。
自慢じゃないが、俺は極度の面倒臭がりやだ。
実のところ、周りでそれを知っている人はすごく少数になると思う。
几帳面でマメなイメージが不思議と付くことが多いのだが、実のところ、典型的なO型の性格。
前も、本屋で立ち読みしていた雑誌の血液型占いのページは、こんな感じだった。
・正義感が強く、情が深い。
・向上心が強く負けず嫌い。
・機嫌が悪いとへそを曲げる。
・地に足のついた現実的な考え方をし、客観視することができる。
・かなりの自信家なので、自分勝手な行動を取りやすい。
実のところ、悔しいことに殆ど当たっているのがなんとも辛いところだった。
そんな俺の性格を熟知した母親は、こうやって困ったときには一応助けの船を出してくれるのだが、こちらが思う100倍は恩着せがましい態度なので、あまり素直に感謝の意を表すことが難しい。
だから、いつだってこんな会話になるんだろう。
「いいから早く片付ければ?」
「うっせー、適当にやりゃいいんだよ。金で解決!」
「・・・仕事でお金使うようになってから、性格悪くなったわね、アンタ」
やっぱり全部否定できないところが悲しいところだ。
9時30分。
そろそろ手持ち無沙汰になってきた頃になって、ようやく引越し業者がやってきた。
「今日はよろしく御願いしますー」
とやってきたのは、25前後と思しき気のよさそうな今時の兄ちゃんだった。
「処分する品と、大きな家具の配置だけ先に確認して運びます。あと貴重品は大丈夫でしょうか?」
「えっと、そのラブソファは部屋の左奥に。あと電子ピアノが・・・」
自分で配置を説明しながら、俺は久々に接する引越し屋さんの手際のよさにひそかに舌を巻いていた。
壁を傷つけないようにさっとボール紙を張り、大きな家具に関しては、ふわっとした素材の保護布を上から被せていく。
トラックで出す順番を瞬時に判断し、重量バランスを計算する。
−こんな仕事でも、創造性の余地があるんだな。
当たり前のことに少し興奮しながら眺めていると、やがて1時間ほどであれだけモノが詰まった部屋も空になった。
さすがに7年住んだだけあって、ポスターの跡や、冷蔵庫の後ろの汚れなどは目に付く。
ガランとした、でも見慣れたその部屋をぼんやり見ていると、母親が後ろから呟いた。
「あれからもう、7年経つんだね」
「あ、だね」
「思えば、今の名古屋の家と変わらないくらい住んでるんだ。長いわね・・・」
そうだった。
名古屋の今の実家に越してきたのが、11歳。
今の家に越してきたのは大学からだから、時間的にはそれほど差異がないわけで、自分の中の時間に対する認識の違いにちょっとぞっとしてしまう。
やっぱり、生きている時間が長くなると、1年に対する感覚が、10分の1から20分の1という形で変化していくからだろうか。
「なんかさ」
「ん?なによ?」
「年とると時間が経つのが早いってホントかもな」
俺がそう言うと、母親は一言「バカ」とだけ言って、誰もいない部屋から出て行った。
もう一度部屋を眺めやる。
西側の窓に残されたマスタード色のブラインドが所在無さげに佇んでいた。
ソファの色と合わせてて結構お気に入りのものだった。
今回、窓のサイズと合わない為に、泣く泣く置き去りにしていくことになったのだが、こうして見ると、意外と引っ越し当初は色合いとか拘ってたんだよな、と今更ながらに思う。
その瞬間、ふと思い出したのは、21歳になりたての冬のことだ。
当時、気になってた大学の同級生が初めて家に遊びに来たんだっけ。
「ふふ、わたしの部屋より広いかもー」
そう言いながら、興味深そうに部屋を見回す彼女。
「広いだけで何も面白いことないけどさ、ゆっくりしていってよ」
と俺は照れながら、電子ピアノに寄り掛かった。
そんな俺を見ながら、彼女が面白そうに言ったのは、色のことだった。
「この部屋、なんだかイエローに統一されてるよね?マスタード色のブラインド、電子ピアノの鮮やかな黄色、あと、このたんぽぽ色のソファ・・・結構意外だな」
「意外ってなにが?」
そう聞きなおした俺に、彼女はちょっと下手クソなウィンクをしながらこう答えた。
「黄色っていうイメージがなかったから。怒らないでね。もっとね、落ち着きとビビッドさが同居してるような色のイメージがあるんだなあ」
「それってジジクサイってことかよ?ひでー女だな」
そう言いながら舌を出した俺に、彼女はちょっと頬を膨らませて、クッションを俺に投げつける。
そのクッションは命中せず、結局ブラインドに音を立ててぶつかった。
あれから何年経ったんだろう。
俺は頭を振りながら、ブラインドを一回そっと触り、それから後ろを振り向かずにドアを閉めた。
自分に合わない色使いだと思ったことはないけど、確かにビビッドなイエローを傍に置いておく習慣は自分になかった気がする。
それなのに、不思議と自分がくつろげる場所にそれを置いてるのは、何かの意識の現われなのだろうか。
「いつまで思い出ごっこしてるの?もう行くんでしょ?」
ドアの向こう側から聞こえる声に生返事を返しつつ、俺は再び立ち上がり、7年間の思い出に蓋をした。
| 2005 |
| 02,24 |
新しい街に立つと、いつだってふわふわとした不思議な気分になる。
期待、不安、孤独、未知への遭遇。
−そして、それでもそこに立つ己への回帰。
そんなどこにも括れないような感情が、行き場をなくして渦巻いているような、落ち着かない時間。
借りてきた猫のように感じられるこの場所も、いずれこう言えるようになるのだろうか。
ただ一言・・・「ただいま」と。
#1 February 24,2005 Tokyo
24日、引越し前日。
俺は、新しく越してくる部屋の中にいた。
7年ぶりの引越しだと思う。
その時分は、特に自分でセッティングした引越しではなかったから、自発的にこうやって居場所を変化させるのは初めてのことだった。
「なんか調子狂うよな、こういうの」
俺はそうつぶやきながら、窓を開き、真新しい馴染みなき景色に浸った。
天の名前を司る不思議な坂が、眼下に広がり、そのさらにずっと向こうには、新宿の高層ビル群が上品ながらも怪しげに、その赤い光を点滅させているのが映る。
何もない部屋。
明日になれば、自分の家具で溢れ出していくこの部屋も、今はただ闇の中で静かにその時を待ち続けている。
まだ自分の存在を視認していないこの空気たちは、いつから俺の部屋としての自我を持つのだろうか。
いつから、そこに俺という記憶が染み出していくのだろう。
そんなことを、ここに来てからずっと考えてしまうのは、家を探すときに起こったある出来事のせいだということは、自分でもよく分かっていた。
そう、忘れもしないあの日のこと、あれは・・・。
・・・ブゥーッブゥーッ。
「やべっ、うとうとしてた」
窓際に置いた携帯に慌てて手を伸ばす。
3コール目になんとか通話ボタンを押せた。
「もしもしー」
「あ、もしもし。私だけど、引越し中ごめんなさい」
「いえいえ、お疲れ様です。こちらこそ私事でマジ申し訳ないです」
俺がそう言うと、電話の向こう側のソプラノボイスが、ケラケラと笑った。
彼女のウェービーな髪が踊るのが目に浮かぶ。
電話の向こう側は、1月からの新しい上司だった。
金融機関でコンサルティングセールスに携わって3年。
転職する同期が増えてきて、ちょっと自身の所在を確かめる機会が多くなった中、俺はここにいることを望み、代わりによりステップアップした仕事に就くことを選んだ。
そういった今までいた自分の立場のような人に対し、そのセールス法のサポートをしたり、発案をしていき、セールスのプランニングを作っていくという仕事だ。
自分が実際に顧客と対面する機会は減るけれど、代わりにそういった目標から離れ、より視野のスプレッドを拡張したり、自分の脳ミソを絞る作業が増えるのは、素直にうれしかった。
周りに「これからだったのに」「勿体無い」と言われるのは、逆にうれしいことなんだと思うようにしている。
今の仕事は、基本的に彼女と自分だけが担当しているという仕事が多く、さらに2人の間でも微妙に担当しているものが違う。
それでも、困ったことを何でも聞けて、新しいことを発案したときに真っ先に持ちかける、仕事柄一番近い関係の人だ。
40近くという年齢を感じさせない(本当に30少々だと思っていた)パワフルかつ柔らかい女性で、こちらに否があることも必ずこちら側に配慮した物言いをしてくれるところが本当にありがたかった。
「それより16時からの会議大丈夫?私でよければ話すけど」
「はい、バッチリ準備してます。携帯から会議には入りますよ」
俺はそう答えながら、鞄の中からパワーポイントの印刷物を取り出した。
自分が昨日急遽作成した資料だった。
本来誰かに頼まれたものでも何でもなかったのだが、ふと思いついたイメージを形にしたくて堪らないという性格は、この仕事ではたまたまプラスに働いているらしい。
マネージメントという観点ではからきしダメな部分の多い自分でも、一人で切り込みながらアイディアを形にしていく今のスタイルは、本来の自分ともうまくマッチングしているんじゃないかと、我ながら思うんだ。
それは、先日行われた高齢者向きのセミナーで、今後の超高齢化時代をどう生きていくかというのを、データと共に提供する、よくありがちなそれのフィードバックだった。
ただ、変わっていたのは、その高齢化の浸透具合に関して、人口学の観点から専門家に講演をしてもらった点だろう。
言葉だけが先行しがちなこの時代において、数字はいい意味でも悪い意味でも特効薬となりやすい。
使い方さえ間違えなければ、啓蒙活動の一環としては一定以上の効果を期待できるはずで、それをスタッフへ徹底させようという、少し顧客に取っては意地の悪いやり方だった。
本来、それを思いついた時点で気付けばよかったのだが、その会議の日こそが今日だった。
引越し準備のために無理言って休みを取ったものの、どうしても自分で責任を持ちたかったらしい。
「・・・無理しちゃだめよ。いつでも言ってくれれば代わるからね」
「はい、ご配慮頂いてすみません。できる限りやってみます」
そう殊勝に答えつつ、そういった類のプレゼンテーションが大好きな俺は、ふと唇の端に笑みを浮かべながら、再度プリントへと目を移した。
スライド8枚を10分。
恐らく配分も展開も大丈夫だと思う。
まあ、気楽にいこうぜ−少し心拍数の上がっている自分の心臓をなだめつつ、ヒンヤリとしたフローリングの床にゴロっと寝転がった。
・・・ブゥーッブゥーッ。
「またかよ・・・」
切った筈の携帯電話が再び震えている。
会議まで残り僅かなので、少しいぶかしみながら電話を取った。
「はいはい、もしもし」
「あのー、4時にお約束した東京ガスの・・・」
その瞬間、俺はさっと顔から血が引いていくのを感じた。
16時、会議の時間。
全国に中継された会議に、俺とガス屋とのやり取りが聞こえたら、それはもう滑稽だ。
「・・・ですから、そうしたY世代の台頭により、X世代における年金確保の問題は・・・」
「すみませーん、ガスの栓なんですが・・・」
「あ、えーと、ですから年金がですね・・・」
そんな会話、想像するだけで反吐が出る。
何かが向上するための道化師にはなるけれど、意味のない道化を演じるほど、柔軟なプライドを持っては生まれてこなかったし。
それからの時間、どう自分が動いたのかさっぱり覚えていない。
ただ覚えていることと言えば、断片的に、モニターに映るガス屋さんの姿を視認しながら、必死にごまかしつつ会議でしゃべったことだけだ。
それでも、しゃべる瞬間だけは、不思議と音もさっと消えて、まるで違うプラネットに浮かんだような気分になったのは忘れられない。
あの世界の感覚を知ってしまっているから、矢面に立つ瞬間をやめられないんだと思う。
−ひょっとしたら、もう中毒なのかもしれない。高揚感という名前のドラッグの。
期待、不安、孤独、未知への遭遇。
−そして、それでもそこに立つ己への回帰。
そんなどこにも括れないような感情が、行き場をなくして渦巻いているような、落ち着かない時間。
借りてきた猫のように感じられるこの場所も、いずれこう言えるようになるのだろうか。
ただ一言・・・「ただいま」と。
24日、引越し前日。
俺は、新しく越してくる部屋の中にいた。
7年ぶりの引越しだと思う。
その時分は、特に自分でセッティングした引越しではなかったから、自発的にこうやって居場所を変化させるのは初めてのことだった。
「なんか調子狂うよな、こういうの」
俺はそうつぶやきながら、窓を開き、真新しい馴染みなき景色に浸った。
天の名前を司る不思議な坂が、眼下に広がり、そのさらにずっと向こうには、新宿の高層ビル群が上品ながらも怪しげに、その赤い光を点滅させているのが映る。
何もない部屋。
明日になれば、自分の家具で溢れ出していくこの部屋も、今はただ闇の中で静かにその時を待ち続けている。
まだ自分の存在を視認していないこの空気たちは、いつから俺の部屋としての自我を持つのだろうか。
いつから、そこに俺という記憶が染み出していくのだろう。
そんなことを、ここに来てからずっと考えてしまうのは、家を探すときに起こったある出来事のせいだということは、自分でもよく分かっていた。
そう、忘れもしないあの日のこと、あれは・・・。
・・・ブゥーッブゥーッ。
「やべっ、うとうとしてた」
窓際に置いた携帯に慌てて手を伸ばす。
3コール目になんとか通話ボタンを押せた。
「もしもしー」
「あ、もしもし。私だけど、引越し中ごめんなさい」
「いえいえ、お疲れ様です。こちらこそ私事でマジ申し訳ないです」
俺がそう言うと、電話の向こう側のソプラノボイスが、ケラケラと笑った。
彼女のウェービーな髪が踊るのが目に浮かぶ。
電話の向こう側は、1月からの新しい上司だった。
金融機関でコンサルティングセールスに携わって3年。
転職する同期が増えてきて、ちょっと自身の所在を確かめる機会が多くなった中、俺はここにいることを望み、代わりによりステップアップした仕事に就くことを選んだ。
そういった今までいた自分の立場のような人に対し、そのセールス法のサポートをしたり、発案をしていき、セールスのプランニングを作っていくという仕事だ。
自分が実際に顧客と対面する機会は減るけれど、代わりにそういった目標から離れ、より視野のスプレッドを拡張したり、自分の脳ミソを絞る作業が増えるのは、素直にうれしかった。
周りに「これからだったのに」「勿体無い」と言われるのは、逆にうれしいことなんだと思うようにしている。
今の仕事は、基本的に彼女と自分だけが担当しているという仕事が多く、さらに2人の間でも微妙に担当しているものが違う。
それでも、困ったことを何でも聞けて、新しいことを発案したときに真っ先に持ちかける、仕事柄一番近い関係の人だ。
40近くという年齢を感じさせない(本当に30少々だと思っていた)パワフルかつ柔らかい女性で、こちらに否があることも必ずこちら側に配慮した物言いをしてくれるところが本当にありがたかった。
「それより16時からの会議大丈夫?私でよければ話すけど」
「はい、バッチリ準備してます。携帯から会議には入りますよ」
俺はそう答えながら、鞄の中からパワーポイントの印刷物を取り出した。
自分が昨日急遽作成した資料だった。
本来誰かに頼まれたものでも何でもなかったのだが、ふと思いついたイメージを形にしたくて堪らないという性格は、この仕事ではたまたまプラスに働いているらしい。
マネージメントという観点ではからきしダメな部分の多い自分でも、一人で切り込みながらアイディアを形にしていく今のスタイルは、本来の自分ともうまくマッチングしているんじゃないかと、我ながら思うんだ。
それは、先日行われた高齢者向きのセミナーで、今後の超高齢化時代をどう生きていくかというのを、データと共に提供する、よくありがちなそれのフィードバックだった。
ただ、変わっていたのは、その高齢化の浸透具合に関して、人口学の観点から専門家に講演をしてもらった点だろう。
言葉だけが先行しがちなこの時代において、数字はいい意味でも悪い意味でも特効薬となりやすい。
使い方さえ間違えなければ、啓蒙活動の一環としては一定以上の効果を期待できるはずで、それをスタッフへ徹底させようという、少し顧客に取っては意地の悪いやり方だった。
本来、それを思いついた時点で気付けばよかったのだが、その会議の日こそが今日だった。
引越し準備のために無理言って休みを取ったものの、どうしても自分で責任を持ちたかったらしい。
「・・・無理しちゃだめよ。いつでも言ってくれれば代わるからね」
「はい、ご配慮頂いてすみません。できる限りやってみます」
そう殊勝に答えつつ、そういった類のプレゼンテーションが大好きな俺は、ふと唇の端に笑みを浮かべながら、再度プリントへと目を移した。
スライド8枚を10分。
恐らく配分も展開も大丈夫だと思う。
まあ、気楽にいこうぜ−少し心拍数の上がっている自分の心臓をなだめつつ、ヒンヤリとしたフローリングの床にゴロっと寝転がった。
・・・ブゥーッブゥーッ。
「またかよ・・・」
切った筈の携帯電話が再び震えている。
会議まで残り僅かなので、少しいぶかしみながら電話を取った。
「はいはい、もしもし」
「あのー、4時にお約束した東京ガスの・・・」
その瞬間、俺はさっと顔から血が引いていくのを感じた。
16時、会議の時間。
全国に中継された会議に、俺とガス屋とのやり取りが聞こえたら、それはもう滑稽だ。
「・・・ですから、そうしたY世代の台頭により、X世代における年金確保の問題は・・・」
「すみませーん、ガスの栓なんですが・・・」
「あ、えーと、ですから年金がですね・・・」
そんな会話、想像するだけで反吐が出る。
何かが向上するための道化師にはなるけれど、意味のない道化を演じるほど、柔軟なプライドを持っては生まれてこなかったし。
それからの時間、どう自分が動いたのかさっぱり覚えていない。
ただ覚えていることと言えば、断片的に、モニターに映るガス屋さんの姿を視認しながら、必死にごまかしつつ会議でしゃべったことだけだ。
それでも、しゃべる瞬間だけは、不思議と音もさっと消えて、まるで違うプラネットに浮かんだような気分になったのは忘れられない。
あの世界の感覚を知ってしまっているから、矢面に立つ瞬間をやめられないんだと思う。
−ひょっとしたら、もう中毒なのかもしれない。高揚感という名前のドラッグの。
カレンダー
プロフィール
カテゴリー
最新記事
(04/18)
(03/17)
(02/15)
(12/15)
(11/15)
最新TB
ブログ内検索