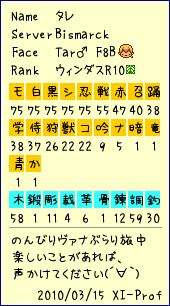| 2005 |
| 08,24 |
«カメ子の恋»
(※ラジオ第2回はこちらからドウゾ)
某所で書いた文章をちらりとご紹介のコーナー。
タイミングよく敵のスタンが来たり、サイレスが来たりと、なかなか敵の攻撃というのはまるで人がいるかのようにいやらしいことが何度もあります。
そのたびに、中の人大変だよな、とかたまにFFやりながら会話にしちゃいますけど。
実際に中の人いたら、ホント大変なのかもしれないですよね。
少なくともミミズとかはやりたくないw
でも、よく考えてみたら、オークにもクゥダフにもちゃんと社会があって、ひょっとしたら彼らも就職したり軍務についたり、はたまた恋をしたり家庭をもったりするのかなって思ったんスよね。
そんあ妄想が広がっちゃって、彼らの視点の小説とか読んでみたいなーと。
誰か【書きませんか?】
・・・誰も書きそうにないので、勝手にちょっと書き出してみますたw
しかし、すごく恐ろしいことになってしまったのでした・・・以下をご覧ください。
「はーあ・・・」
わたしは、鏡の前で一つため息をついた。
毎朝、こうして鏡を見るたびに、己の姿を呪いたくなる。
ピンク色に上気した頬も、少し線の細くなった顎のラインも、何よりいとおしい自分の一部だ。
なのに、どうしてわたしの背中には、びっちりと堅い殻がまとわりついているんだろう。
「なんでわたし、こうなっちゃったのかな・・・」
女だってたまには露出の多い服だって着てみたい。
雨季と乾季の狭間には、ベドーにも少しだけギラギラした夏がやってくる−それなのにわたしときたら、毎年その殻に身を竦め、日焼けしないようにとフェイスケアに勤しむだけ。
「カメ子・・・」
最近モーションをかけてくるのは、アダマン王の側近のルビーだった。
連続魔の使い手として、クゥダフ族の中でも名高いルビーも、わたしにとっては単にしつこさに食傷気味のくだらない男の1人。
「わたしなんかよりプラチナちゃんに声かけてみればいいじゃない」
「いいんだよ、俺にはお前しかいない。お前と100人の子供を作ってラブラブと幸せに・・・」
そこまで聞いた時点でわたしは、腰のハンマーを振り上げ、彼の頭を殴りつけた。
ドオッと音を立てて崩れる音に一瞬わたしは顔を顰め、彼の冥福を祈った。
彼が手に握り締めているルビーをそっと取り上げ、わたしは禁じられたあの場所へと向かう。
彼の大きな体がやがて視界から消えるのを確認した後、ブロンズの色に覆われた洞窟で、わたしはそっとリンクパールを取り上げた。
「もしもし・・・わたし」
「久しぶりだな。全国獣人サブリガン大会以来、か?」
懐かしい声がした。毎晩のように耳の奥で響くその温かな声。
「ええ・・・ずっと会いたかった・・・」
「仕方ないだろ、ヤグードとクゥダフが結ばれたなんて知ったら、ツェー・シジュ様になんていわれるか・・・」
「いいの、そんなこと・・・だって、もうあなたと出会う前から、わたしはあなたに惹かれる運命だったから。覚悟してるのよ、そんなこと」
彼が息を呑む音が聞こえる。そんな彼の実直さに、わたしは胸の奥がじんと切なく痛む音を聞いた気がした。
細長い首のラインや、切れ長の鋭い目が思い出される度、胸をかきむしりたくなるほどの愛おしさに思わず焦がれてしまうのに、彼の前となったらもう何もかも投げ出してしまいたい衝動に駆られる。
こんな感覚は、本当に生まれて初めてのことだった。
しかし、そんなわたしにも覚悟を決めるときというのがある。それがまさに今この瞬間だということを、誰に教わるでもなく、わたしは感じていた。
「ルビーを・・・殺したわ」
「ほ、ほんとか?お前ってやつは・・・。これでアダマンキングからも追われる身になることを分かっているのか?」
「・・・仕方なかったのよ、クゥダフってやつは一度執着したらいつまでも音を追ってやってくるから」
「俺も覚悟はできているさ。魔晶石のことは知ってるな?逃げるなら、それの確保が前提となる」
「どうして?そんな暇ないでしょう?」
「黙って聞くんだ。俺には作戦がある。ツェー・シジュ様もアダマン王もそれぞれの場所に拘る理由はただ1つ。その石さ」
だから、と彼は言葉をつぐ。
「その石さえ確保してしまえばこちらのものだ。それにひょっとしたら俺とお前も・・・」
しかし、その瞬間、彼からの通信は途絶えてしまった。最後に聞こえたのは、吟遊詩人らしき楽器の音と、アサシンの使う忍術の気配だけ。
そして、しばらくしてザーっという音が聞こえた後、ふっつりと音が消えた。
どれだけの時間が経過したのだろうか。
「・・・う、うう・・・」
その空間に木霊する声が自分のものと意識するまでには、しばしの時間を必要とした。
わたしは、全て失ってしまったのだろうか。どこで間違えてしまったんだろう。
会いたいよ、ねぇ、会いたいよ・・・。
「そこまでだ、カメ子」
次回、「カメ子の恋」最終回、「出せない手紙」お楽しみに。なんちてw
即興で書いたら想像してイヤな気持ちになりました(ノ∀`)
皆さんもこういうの書きません?w
某所で書いた文章をちらりとご紹介のコーナー。
タイミングよく敵のスタンが来たり、サイレスが来たりと、なかなか敵の攻撃というのはまるで人がいるかのようにいやらしいことが何度もあります。
そのたびに、中の人大変だよな、とかたまにFFやりながら会話にしちゃいますけど。
実際に中の人いたら、ホント大変なのかもしれないですよね。
少なくともミミズとかはやりたくないw
でも、よく考えてみたら、オークにもクゥダフにもちゃんと社会があって、ひょっとしたら彼らも就職したり軍務についたり、はたまた恋をしたり家庭をもったりするのかなって思ったんスよね。
そんあ妄想が広がっちゃって、彼らの視点の小説とか読んでみたいなーと。
誰か【書きませんか?】
・・・誰も書きそうにないので、勝手にちょっと書き出してみますたw
しかし、すごく恐ろしいことになってしまったのでした・・・以下をご覧ください。
「はーあ・・・」
わたしは、鏡の前で一つため息をついた。
毎朝、こうして鏡を見るたびに、己の姿を呪いたくなる。
ピンク色に上気した頬も、少し線の細くなった顎のラインも、何よりいとおしい自分の一部だ。
なのに、どうしてわたしの背中には、びっちりと堅い殻がまとわりついているんだろう。
「なんでわたし、こうなっちゃったのかな・・・」
女だってたまには露出の多い服だって着てみたい。
雨季と乾季の狭間には、ベドーにも少しだけギラギラした夏がやってくる−それなのにわたしときたら、毎年その殻に身を竦め、日焼けしないようにとフェイスケアに勤しむだけ。
「カメ子・・・」
最近モーションをかけてくるのは、アダマン王の側近のルビーだった。
連続魔の使い手として、クゥダフ族の中でも名高いルビーも、わたしにとっては単にしつこさに食傷気味のくだらない男の1人。
「わたしなんかよりプラチナちゃんに声かけてみればいいじゃない」
「いいんだよ、俺にはお前しかいない。お前と100人の子供を作ってラブラブと幸せに・・・」
そこまで聞いた時点でわたしは、腰のハンマーを振り上げ、彼の頭を殴りつけた。
ドオッと音を立てて崩れる音に一瞬わたしは顔を顰め、彼の冥福を祈った。
彼が手に握り締めているルビーをそっと取り上げ、わたしは禁じられたあの場所へと向かう。
彼の大きな体がやがて視界から消えるのを確認した後、ブロンズの色に覆われた洞窟で、わたしはそっとリンクパールを取り上げた。
「もしもし・・・わたし」
「久しぶりだな。全国獣人サブリガン大会以来、か?」
懐かしい声がした。毎晩のように耳の奥で響くその温かな声。
「ええ・・・ずっと会いたかった・・・」
「仕方ないだろ、ヤグードとクゥダフが結ばれたなんて知ったら、ツェー・シジュ様になんていわれるか・・・」
「いいの、そんなこと・・・だって、もうあなたと出会う前から、わたしはあなたに惹かれる運命だったから。覚悟してるのよ、そんなこと」
彼が息を呑む音が聞こえる。そんな彼の実直さに、わたしは胸の奥がじんと切なく痛む音を聞いた気がした。
細長い首のラインや、切れ長の鋭い目が思い出される度、胸をかきむしりたくなるほどの愛おしさに思わず焦がれてしまうのに、彼の前となったらもう何もかも投げ出してしまいたい衝動に駆られる。
こんな感覚は、本当に生まれて初めてのことだった。
しかし、そんなわたしにも覚悟を決めるときというのがある。それがまさに今この瞬間だということを、誰に教わるでもなく、わたしは感じていた。
「ルビーを・・・殺したわ」
「ほ、ほんとか?お前ってやつは・・・。これでアダマンキングからも追われる身になることを分かっているのか?」
「・・・仕方なかったのよ、クゥダフってやつは一度執着したらいつまでも音を追ってやってくるから」
「俺も覚悟はできているさ。魔晶石のことは知ってるな?逃げるなら、それの確保が前提となる」
「どうして?そんな暇ないでしょう?」
「黙って聞くんだ。俺には作戦がある。ツェー・シジュ様もアダマン王もそれぞれの場所に拘る理由はただ1つ。その石さ」
だから、と彼は言葉をつぐ。
「その石さえ確保してしまえばこちらのものだ。それにひょっとしたら俺とお前も・・・」
しかし、その瞬間、彼からの通信は途絶えてしまった。最後に聞こえたのは、吟遊詩人らしき楽器の音と、アサシンの使う忍術の気配だけ。
そして、しばらくしてザーっという音が聞こえた後、ふっつりと音が消えた。
どれだけの時間が経過したのだろうか。
「・・・う、うう・・・」
その空間に木霊する声が自分のものと意識するまでには、しばしの時間を必要とした。
わたしは、全て失ってしまったのだろうか。どこで間違えてしまったんだろう。
会いたいよ、ねぇ、会いたいよ・・・。
「そこまでだ、カメ子」
次回、「カメ子の恋」最終回、「出せない手紙」お楽しみに。なんちてw
即興で書いたら想像してイヤな気持ちになりました(ノ∀`)
皆さんもこういうの書きません?w
PR
| 2005 |
| 08,06 |
(ラジオはこちらのエントリーからどうぞ・v・)
「すまん、パクララ・・・これを・・・頼む」
「お父さん!そんなの嫌・・・」
「いいかい、これはお前を必ず導く光となるものだ。手放さず持っておくんだよ・・・」
父の意識が消えたとき、私はまだ冒険者見習いにもなっていなかった。
14歳の夏、ただ蝉の咽び泣くような声だけが私の記憶になった。
それでも、夏が来るたびに手にした鏡を見て思うのだ。
これは、本当に導きの光なのだろうか、と。
ベッドから立ち上がり、窓をさっと開けた。
夏とはいえ、ジュノの風は少し冷たい。
あれから片手で収まらないほどの年月が経過し、私も冒険者見習いを経て、やがて戦士として細々と生計を立てていけるようにはなった。
それでも、父が遺した鏡が何を導いてくれているのかは今でもよくわからない。
いや、わからなくなったのだ・・・。
「ねぇ、どうしたらいいと思う?」
鏡の奥では綺麗にそろえられた前髪の女が暗い目で私を覗き込んでいた。
−ああ、これが私。
よろよろと窓にもたれ掛かり、私はため息をついた。
力さえあれば何でもできると思っていたあの頃。
実際には、力を蓄えていくほどに自分の無力さがわかるだけだというのに。
「なんでここにいるんだろう、私・・・」
海からあがる潮風は、私に何も語ってはくれなかった。
翌日。
私は、鏡が発する不穏な気配に導かれて、エルディーム古墳へと潜入した。
過去の大戦で亡くなった諸侯達が眠るといわれるこの古墳、当時はとてもいい状態で眠りにつけたとは言えなかったようで、亡霊の気配がすると冒険者の間でも語り草になっている場所だ。
私も、今の自分が一人で歩くには少々心細い場所だったが、珍しく鏡が強い光を放ったこともあって、壁に手を付きながら微かにともった灯りを頼りに奥へと進む。
タルタルの私に取って、こういう場所は視界が狭くて非常に苦手な場所だ。
と、ジュルッという粘着質な音と同時に、熱がこちらに向かって飛んできた。
「これはファイガ・・・!」
だめだ、防ぎきれない!
目を伏せること、一秒、二秒・・・。
しかし、一向に熱は私を襲ってこなかった。
目を開けると、目の前には私の同じタルタル族の少年が己の拳に熱を収束させ、奥にいるヘクトアイズを殴りつけているところだった。
2,3発の拳であっという間にヘクトアイズが倒れる。
彼が、噂に聞く格闘家、モンクなのだろうか。
拳にすべてを賭けるアタッカーの中のアタッカー。
なんて強さなの・・・。
「あの・・・」
私が声をかけようとすると、彼はにっこりと微笑み、無言で闇の中へと姿を消した。
少し赤のグラデーションがかかった金色の髪が微かに揺れるのが見えた。
「・・・おかあさん・・・ヒック・・・」
彼と別れ歩いていると、どこからか子供の泣き声が聞こえてきた。
曲がり角の向こうから現れたのは、まだ年端も行かないヒューム族の少女の姿。
「どうしたの?もう大丈夫」
「うえぇぇん、おかあさん・・・」
私は彼女の頬の煤をそっと払ってやり、手を取ろうとした。
その瞬間−。
「危ないッ、気をつけろ!」
後ろから飛んできた声に咄嗟に子供を胸に抱え、横へと飛ぶ。
ザシュッ!
錆び付いた片手剣が私のいた場所へと突き刺さる。
立ち上がる砂埃の向こうには、スケルトン族の憎悪に篭った目と、先ほど私を助けてくれたタルタルのモンクの姿があった。
「その子供は任せた。こっちは俺に任せて」
彼はそういうと、立ち上がり、ナックルを上にポンポンと軽やかに宙に放り投げ、己の拳へと装着した。
こんな場面にも慣れているのだろうか、汗ひとつかいていない。
と、その瞬間、私の懐の鏡が、じんわりと熱を持った。
慌てて取り出すと、それは確かに彼を柔らかな光で包んでいる。
「な、なに・・・?」
「いいか、子供を頼むぞ」
彼の声に慌てて前を見やると、身長の何倍もあるスケルトンが彼を襲うところだった。
「危ないッ!」
慌てて私が挑発しようとすると、彼は拳をギリギリのところで掻い潜り、裏から拳を繰り出した。
「カウンター、これがモンクの極意さ。よかったら一緒に加勢してくれ」
その言葉に私は、ここ最近ずっと悩んでいたことがちょっとずつ収斂していく瞬間に立ち会っている気がしたんだ。
その想いの正体に行き当たったのはもう少し後のことだったけれど、私は少なくともその瞬間、彼と一緒に剣を振り上げるその瞬間を、とてもとても愛おしく感じられたのだった。
やがてスケルトンが崩れ落ちる音と共に、私たちは武器を納めた。
子供が泣きじゃくりながら私にすがり付いてくる。
この年の子供が古墳に迷い込んだら、下手すればトラウマにもなり兼ねない。
こうした一般の人たちのケアをするのも我々冒険者の務めだ。
「先にこの子を連れて帰ります。あなたは?」
「ああ、俺もスケルトンの欠片を収集したら依頼人に報告に行かないと。ありがとう、パクララ」
「えっ、なんで私の名前を?」
私が驚いて彼の顔を見やると、彼は金色の頭を照れくさそうにかきながら、こう答えたのだった。
「君を探すのが、俺の受けた依頼だったんだよ。後でよかったら上層の倉庫前まで来てくれないか?」
−縁とは、かくも狭きものだ、と私は一人ごちる。
そう、鏡が導いたのがひょっとしたら場所ではなくて、人だったとしたら、それもまたひとつの縁と呼べるのかもしれない。
私には、それを確かめる必要があった。
ジュノ上層。
工業地区として昼間は活発な空気を漂わせるこの場所も、夜は少しばかりその喧騒も収まる。
そして、倉庫の一角で、そのやわらかい表情を浮かべたミスラが私を待っていた。
「あなたがパクララさんね・・・。一つ私の話を聞いてくれない?」
彼女の話は、好奇心旺盛なミスラらしいものだ。
つまりは、私の持っている鏡に興味があるということ。しかし−。
「この鏡を譲ることはできません。父の形見のこの鏡があるから、私は冒険者でいられるのですから」
私は彼女が予想しているであろう答えを口にした。
立ち去ろうとしたとき、彼女は思いがけない言葉を口にした。
「ええ、それはわかっているわ。私があなたに御願いしたいのは別のこと」
「えっ?」
「この鏡は、東方の国より齎された恐るべき魔力のものだといわれているわ。しかし、鏡の中には冒険者の意思すらも凌駕する強力なものもあるとか・・・私は、そんな鏡を求めて旅をしているの。もちろん悪用するつもりではないのだけど・・・よかったら、あなたの導きの鏡の力を借してくれないかしら?」
彼女がその鏡で何をするかを聞くのは、いくらなんでも野暮というものだろう。
それに、先ほどまで一緒だったタルタルのモンクの少年も、どうやら彼女のことはある程度認めている様子だったということもあって、私は彼女の依頼を受けることにした。
5日後、そのミスラから連絡が入った。
サンドリア周辺で怪しい鏡の情報があったというのだ。
私は、チョコボを走らせ、サンドリアへと急いだ。
天候にも恵まれたこともあり、半日もかからないうちにロンフォールの森が見えてくる。
「そろそろいいかしら?」
懐の鏡を取り出すと、鏡の光はサンドリア王国ではなく、そこから北西の方角へと伸びていった。
これは・・・ゲルスパ砦?
そう、これにオーク族が絡んでいたとなれば話はわかる。
サンドリアで鏡を見かけただけなら、おそらく彼女は商人に何らかの委託をしたことだろう。
それを避け、私のような冒険者に頼んだのは、何も鏡のことだけじゃない。
おそらく、こうした事態を予見していたのだろう。
相変わらずミスラという種族は強かだ、と私は心の中で密かに舌を巻いた。
グォォォォォッ!
ゲルスパ砦に潜入した途端、大きな雷鳴のような音が響き渡る。
この空気は一度だけ感じたことがあった。2ヶ月ほど前に請け負った国からのミッションで出会った強大なその敵。
「・・・そう、ドラゴンだ。パクララ、力を貸してくれる?」
「あなた・・・」
後ろから静かに歩み寄ってきたのは、タルタルの少年だった。
そう、古墳で出会った小さな格闘家。
彼もやはりここに導かれてきたのだろうか?
「どうやら鏡によって負のエネルギーがコントロールされているらしい。とはいえ、まずはあいつから倒さざるをえない、か・・・」
彼は一人ごちりながら、首を横にふり、次の瞬間、一気に飛んだ。

「サンドリアの子供を一人殺したな?許さねぇ・・・」
彼はそう言いながら温まった拳を一回ため、次の瞬間、ドラゴンの腹部へと何度も拳を往復させ、後ろへと宙返りをする。
「うぉぉぉ、コンボッ!」
どおっと音を立てながら、ドラゴンは崩れ落ちた。
そして、その足元には、割れた鏡が無残な姿を残して転がっている。
「子供が殺された・・・?」
「ああ、さっきロンフォールの森で遺体を見つけたんだ。あれはオークの手によるものではなかった。こんな鏡に殺されるなんて・・・」
「冒険者って・・・結局何もできないのかしら」
私は足元の鏡を拾い上げながらそう呟く。
そう、導きの鏡があろうがなかろうが、結局私に出来ることなど何もなかったのだ。
今までも、そしてこれからも。
「・・・そんなこと言うなよ。
あの古墳で助けてあげた子供に昨日会ったんだ。その子、隣の家の子がケガしているのを見て、自分のハンカチをその子に巻いて手当てをしていたよ。
誰のおかげだと思う?」
「えっ?」
「『親切な冒険者さんが、私にもこうしてくれたから』だってさ。
まだ俺たちに出来ることってたくさんあるんじゃないのかな?
人一人を幸せにするってとても難しいけれど、そんな何でもない行動の積み重ねがきっと人を幸せにする大切な行動なんだ。だからこそ、俺たちは冒険者なんだぜ?」
ああ、満たされるってこういう感情なんだ−そのとき、私は初めてそんな気持ちに触れた。
だから、そのとき鏡が示していたことにようやく思い当たったんだ。
「・・・あなたが映ってる。あなたには何かがあるみたい」
「えっ?」
驚く彼に向かって、私はやっとこの言葉が言えた。
「一緒に冒険に向かいましょうよ?だって私たちは冒険者ですもの」
「すまん、パクララ・・・これを・・・頼む」
「お父さん!そんなの嫌・・・」
「いいかい、これはお前を必ず導く光となるものだ。手放さず持っておくんだよ・・・」
父の意識が消えたとき、私はまだ冒険者見習いにもなっていなかった。
14歳の夏、ただ蝉の咽び泣くような声だけが私の記憶になった。
それでも、夏が来るたびに手にした鏡を見て思うのだ。
これは、本当に導きの光なのだろうか、と。
ベッドから立ち上がり、窓をさっと開けた。
夏とはいえ、ジュノの風は少し冷たい。
あれから片手で収まらないほどの年月が経過し、私も冒険者見習いを経て、やがて戦士として細々と生計を立てていけるようにはなった。
それでも、父が遺した鏡が何を導いてくれているのかは今でもよくわからない。
いや、わからなくなったのだ・・・。
「ねぇ、どうしたらいいと思う?」
鏡の奥では綺麗にそろえられた前髪の女が暗い目で私を覗き込んでいた。
−ああ、これが私。
よろよろと窓にもたれ掛かり、私はため息をついた。
力さえあれば何でもできると思っていたあの頃。
実際には、力を蓄えていくほどに自分の無力さがわかるだけだというのに。
「なんでここにいるんだろう、私・・・」
海からあがる潮風は、私に何も語ってはくれなかった。
翌日。
私は、鏡が発する不穏な気配に導かれて、エルディーム古墳へと潜入した。
過去の大戦で亡くなった諸侯達が眠るといわれるこの古墳、当時はとてもいい状態で眠りにつけたとは言えなかったようで、亡霊の気配がすると冒険者の間でも語り草になっている場所だ。
私も、今の自分が一人で歩くには少々心細い場所だったが、珍しく鏡が強い光を放ったこともあって、壁に手を付きながら微かにともった灯りを頼りに奥へと進む。
タルタルの私に取って、こういう場所は視界が狭くて非常に苦手な場所だ。
と、ジュルッという粘着質な音と同時に、熱がこちらに向かって飛んできた。
「これはファイガ・・・!」
だめだ、防ぎきれない!
目を伏せること、一秒、二秒・・・。
しかし、一向に熱は私を襲ってこなかった。
目を開けると、目の前には私の同じタルタル族の少年が己の拳に熱を収束させ、奥にいるヘクトアイズを殴りつけているところだった。
2,3発の拳であっという間にヘクトアイズが倒れる。
彼が、噂に聞く格闘家、モンクなのだろうか。
拳にすべてを賭けるアタッカーの中のアタッカー。
なんて強さなの・・・。
「あの・・・」
私が声をかけようとすると、彼はにっこりと微笑み、無言で闇の中へと姿を消した。
少し赤のグラデーションがかかった金色の髪が微かに揺れるのが見えた。
「・・・おかあさん・・・ヒック・・・」
彼と別れ歩いていると、どこからか子供の泣き声が聞こえてきた。
曲がり角の向こうから現れたのは、まだ年端も行かないヒューム族の少女の姿。
「どうしたの?もう大丈夫」
「うえぇぇん、おかあさん・・・」
私は彼女の頬の煤をそっと払ってやり、手を取ろうとした。
その瞬間−。
「危ないッ、気をつけろ!」
後ろから飛んできた声に咄嗟に子供を胸に抱え、横へと飛ぶ。
ザシュッ!
錆び付いた片手剣が私のいた場所へと突き刺さる。
立ち上がる砂埃の向こうには、スケルトン族の憎悪に篭った目と、先ほど私を助けてくれたタルタルのモンクの姿があった。
「その子供は任せた。こっちは俺に任せて」
彼はそういうと、立ち上がり、ナックルを上にポンポンと軽やかに宙に放り投げ、己の拳へと装着した。
こんな場面にも慣れているのだろうか、汗ひとつかいていない。
と、その瞬間、私の懐の鏡が、じんわりと熱を持った。
慌てて取り出すと、それは確かに彼を柔らかな光で包んでいる。
「な、なに・・・?」
「いいか、子供を頼むぞ」
彼の声に慌てて前を見やると、身長の何倍もあるスケルトンが彼を襲うところだった。
「危ないッ!」
慌てて私が挑発しようとすると、彼は拳をギリギリのところで掻い潜り、裏から拳を繰り出した。
「カウンター、これがモンクの極意さ。よかったら一緒に加勢してくれ」
その言葉に私は、ここ最近ずっと悩んでいたことがちょっとずつ収斂していく瞬間に立ち会っている気がしたんだ。
その想いの正体に行き当たったのはもう少し後のことだったけれど、私は少なくともその瞬間、彼と一緒に剣を振り上げるその瞬間を、とてもとても愛おしく感じられたのだった。
やがてスケルトンが崩れ落ちる音と共に、私たちは武器を納めた。
子供が泣きじゃくりながら私にすがり付いてくる。
この年の子供が古墳に迷い込んだら、下手すればトラウマにもなり兼ねない。
こうした一般の人たちのケアをするのも我々冒険者の務めだ。
「先にこの子を連れて帰ります。あなたは?」
「ああ、俺もスケルトンの欠片を収集したら依頼人に報告に行かないと。ありがとう、パクララ」
「えっ、なんで私の名前を?」
私が驚いて彼の顔を見やると、彼は金色の頭を照れくさそうにかきながら、こう答えたのだった。
「君を探すのが、俺の受けた依頼だったんだよ。後でよかったら上層の倉庫前まで来てくれないか?」
−縁とは、かくも狭きものだ、と私は一人ごちる。
そう、鏡が導いたのがひょっとしたら場所ではなくて、人だったとしたら、それもまたひとつの縁と呼べるのかもしれない。
私には、それを確かめる必要があった。
ジュノ上層。
工業地区として昼間は活発な空気を漂わせるこの場所も、夜は少しばかりその喧騒も収まる。
そして、倉庫の一角で、そのやわらかい表情を浮かべたミスラが私を待っていた。
「あなたがパクララさんね・・・。一つ私の話を聞いてくれない?」
彼女の話は、好奇心旺盛なミスラらしいものだ。
つまりは、私の持っている鏡に興味があるということ。しかし−。
「この鏡を譲ることはできません。父の形見のこの鏡があるから、私は冒険者でいられるのですから」
私は彼女が予想しているであろう答えを口にした。
立ち去ろうとしたとき、彼女は思いがけない言葉を口にした。
「ええ、それはわかっているわ。私があなたに御願いしたいのは別のこと」
「えっ?」
「この鏡は、東方の国より齎された恐るべき魔力のものだといわれているわ。しかし、鏡の中には冒険者の意思すらも凌駕する強力なものもあるとか・・・私は、そんな鏡を求めて旅をしているの。もちろん悪用するつもりではないのだけど・・・よかったら、あなたの導きの鏡の力を借してくれないかしら?」
彼女がその鏡で何をするかを聞くのは、いくらなんでも野暮というものだろう。
それに、先ほどまで一緒だったタルタルのモンクの少年も、どうやら彼女のことはある程度認めている様子だったということもあって、私は彼女の依頼を受けることにした。
5日後、そのミスラから連絡が入った。
サンドリア周辺で怪しい鏡の情報があったというのだ。
私は、チョコボを走らせ、サンドリアへと急いだ。
天候にも恵まれたこともあり、半日もかからないうちにロンフォールの森が見えてくる。
「そろそろいいかしら?」
懐の鏡を取り出すと、鏡の光はサンドリア王国ではなく、そこから北西の方角へと伸びていった。
これは・・・ゲルスパ砦?
そう、これにオーク族が絡んでいたとなれば話はわかる。
サンドリアで鏡を見かけただけなら、おそらく彼女は商人に何らかの委託をしたことだろう。
それを避け、私のような冒険者に頼んだのは、何も鏡のことだけじゃない。
おそらく、こうした事態を予見していたのだろう。
相変わらずミスラという種族は強かだ、と私は心の中で密かに舌を巻いた。
グォォォォォッ!
ゲルスパ砦に潜入した途端、大きな雷鳴のような音が響き渡る。
この空気は一度だけ感じたことがあった。2ヶ月ほど前に請け負った国からのミッションで出会った強大なその敵。
「・・・そう、ドラゴンだ。パクララ、力を貸してくれる?」
「あなた・・・」
後ろから静かに歩み寄ってきたのは、タルタルの少年だった。
そう、古墳で出会った小さな格闘家。
彼もやはりここに導かれてきたのだろうか?
「どうやら鏡によって負のエネルギーがコントロールされているらしい。とはいえ、まずはあいつから倒さざるをえない、か・・・」
彼は一人ごちりながら、首を横にふり、次の瞬間、一気に飛んだ。

「サンドリアの子供を一人殺したな?許さねぇ・・・」
彼はそう言いながら温まった拳を一回ため、次の瞬間、ドラゴンの腹部へと何度も拳を往復させ、後ろへと宙返りをする。
「うぉぉぉ、コンボッ!」
どおっと音を立てながら、ドラゴンは崩れ落ちた。
そして、その足元には、割れた鏡が無残な姿を残して転がっている。
「子供が殺された・・・?」
「ああ、さっきロンフォールの森で遺体を見つけたんだ。あれはオークの手によるものではなかった。こんな鏡に殺されるなんて・・・」
「冒険者って・・・結局何もできないのかしら」
私は足元の鏡を拾い上げながらそう呟く。
そう、導きの鏡があろうがなかろうが、結局私に出来ることなど何もなかったのだ。
今までも、そしてこれからも。
「・・・そんなこと言うなよ。
あの古墳で助けてあげた子供に昨日会ったんだ。その子、隣の家の子がケガしているのを見て、自分のハンカチをその子に巻いて手当てをしていたよ。
誰のおかげだと思う?」
「えっ?」
「『親切な冒険者さんが、私にもこうしてくれたから』だってさ。
まだ俺たちに出来ることってたくさんあるんじゃないのかな?
人一人を幸せにするってとても難しいけれど、そんな何でもない行動の積み重ねがきっと人を幸せにする大切な行動なんだ。だからこそ、俺たちは冒険者なんだぜ?」
ああ、満たされるってこういう感情なんだ−そのとき、私は初めてそんな気持ちに触れた。
だから、そのとき鏡が示していたことにようやく思い当たったんだ。
「・・・あなたが映ってる。あなたには何かがあるみたい」
「えっ?」
驚く彼に向かって、私はやっとこの言葉が言えた。
「一緒に冒険に向かいましょうよ?だって私たちは冒険者ですもの」
| 2005 |
| 06,28 |
«未来»

「天体観測ってしたことある?」
「天体観測?小学校のとき屋上で見たくらいだな」
僕の返事に、彼女はちょっぴり失望したような表情を浮かべた。
よく見ると、いつからか、彼女の目の奥に光るものが見える。
梅雨時の空模様のせいで、ちょっぴり膨らんだクセのあるダークレッドの髪の毛をクルクルと指に巻きつけながら、彼女は上を見上げた。
見えたのは星でも月でもなくて、単なる鉄パイプと鉄骨でできた人工的な空間だった。
7月の呼び声が近づいてくる6月の終わり。
今年は、梅雨らしい日というのをおおよそ感じられなかった。
雨嫌いの自分にとっては、ちょっぴりほっとしながら、朝焼けの空を見上げてた気がする。
不透明な空ってのはどこか不安だけが浮き彫りになるみたいで、思わず自分の鬱な側面を向かい合うことになっちまうのがたまらなく嫌だった。
そんな雨とも無縁だと思って出かけた週末の日曜日。
普段行きなれない渋谷にCDなんて買いにいこうと思ったのが間違いだったのだろうか。
首筋にふと冷たい感触を覚えたのがつい先ほどのこと。
目的のCDショップに行き着く前に既に音を立てて落ちてきた水音に終われるように、僕は近くの家電量販品へと逃げ込んだ。
−そして、たまたま天体望遠鏡コーナーのところでばったりと出会ったのが、クラスメートのユウだったのだ。
「珍しいな、雨宮も。日曜は勉強とかしてるんだと思ってた」
「う、やっぱり未来くんもそう見える?そんなガリ勉じゃないよ、わたし」
そういいながら、端正なその顔に少ししわを寄せて笑う雨宮ユウの姿は、確かにクラスでいつも見せる優等生の表情とは違って、やわらかく、そしてお世辞抜きでも可愛いと思う。
学校での彼女は、ガリ勉というよりは、どこか近寄りがたい、冬の朝のような空気を纏っていて、僕のみならずクラスの男子は声をかけるやつさえ少なかった。
もっとも、高2になっても未だ色恋沙汰とは凡そ縁のない僕が、本当の雨宮の姿を知らなかったとしても無理はないのだろうけど。
ちなみに、「未来くん」ってのは渾名じゃなく、僕の本名だ。
水無未来という本名を口に出しても、一度で理解されることは少ない。
いつもは照れくささを力づくで抑えてしまいたくなるその名前だけど、普段と違うシチューエションで、女の子から発音されると、意外にも悪い気がしないもんだな、と僕はどこか熱っぽくなる自分を意識していた。
「あ、雨宮は何してるんだ?こんなところで」
「・・・ちょっとね、お買い物に寄ったついでに、コレを見に来たんだ」
そう言いながら彼女が指差したのは、白く丸いフォームが印象的な天体望遠鏡だった。
こんなもの見たのは、いつ以来のことだったんだろう。
そして、彼女は少し目をそらした後、もう一度僕の目を覗き込むようにこう言った。
「未来くん、天体観測ってしたことある?」
その続きが、冒頭のシーンというわけだったんだ。
天体観測といって思い出すのは、バンプオブチキンの曲といったレベルの僕にとって、彼女のその翳った表情は予想外のことだった。
もともと女の子と話すことに慣れてないせいもあって、思わずうろたえてしまう。
「い、いや、その、天体観測、いいと思うよ。ほら、しし座流星群とかなら、ちょっとベランダから姉貴と一緒に見たことあるし・・・」
正確には姉貴が見ていた、だけなのだが、心の中で姉ちゃんごめん、と一言謝っておいた。
僕の必死の答えにも彼女は特に反応を示さず、天体望遠鏡を一撫でし、やがてショートカットの髪の毛を揺らして出口の方向へと立ち去った。
ざーっと雨の音だけが戸口の方から音を増して、僕の耳に突き刺さる。
結局僕はビニール傘を購入し、出口の方へと足を踏み出した。
ユウは戸口に立ち、落ちてくる雨粒の等加速度運動を計算するかのように、じっと薄暗い空を見つめている。
「・・・やまないな、雨」
「うん」
よかった、シカトされなかった、と僕はちょっと胸を撫で下ろしながら、ほらよ、と傘を差し出す。
「え?これ今買ったの?」
「必要なら使ってくれればいいよ。オレが送っていきたいところだけど、また怒らせるのイヤだし」
昔からつい言わなくていいことを言ってしまうのが僕の悪いクセだった。
また変なこと言ってしまった、と思いつつ彼女の方を見ると、彼女は意外にも傘をそのまま握り締めたまま・・・なぜか片側の手で僕の手を取った。
「未来くんごめん・・・ちょっとだけいい?」
女の子の手って柔らかいな。
ショートしてる頭はそんな言葉だけをぐるぐるとかき回す。
僕は、しびれた片側の手をできるだけ意識しないようにして、狭いビニールの傘に彼女と僕の身体を押し込めて、すぐ近くのカフェへと走った。
ちょっぴり上を見たり、はたまた下を見てグルグルとアイスラテをストローでかき回すユウが落ち着いたのは、それからたっぷり20分してからのことだった。
「ごめん、わたし変だったでしょ・・・実はね、さっきお父さんとケンカしてきたの」
「ケンカ?」
意外な展開に僕は思わずその言葉を聞き返した。
彼女は黙ってかぶりを振ると、再びストローをぐるぐるとかき回した。
既にアイスラテは泡だってしまっていたけれど、僕は何も言わずに彼女の冷たい手の温度だけを感じていた。
「わたし、小さい頃から星が好きでね。いずれは天体観測の研究をして、宇宙開発の分野なんかとも連携を取っていきたいなって思ってるんだ」
「でも、さっきお父さんにこっぴどく怒られちゃった。趣味と本業を見失うやつがあるかって・・・なんだか泣きたかったけど、わたしも素直じゃないからそういう自分がいるのもイヤで、飛び出してきちゃった」
成績優秀、容姿端麗なんていうマンガに出てくるようなキャラそのまんまの彼女の口からそんな言葉が出てくるのが意外で、僕は汗をかいたフラペチーノの器をそっと引き寄せながら、自分の環境を思い起こしていた。
僕と同じだけの年数しか生きてない彼女が、こんなにも真摯に、真剣に自分の将来について考えてることに、僕は何よりもびっくりしたんだ。
それに引き換え、僕ときたら、背も普通で、勉強だって大して目立つことはない。
今時っぽいランダムカットの頭、ファッションは古着中心だけど、別に特別オシャレなわけじゃないし。
適当に好きなバンドのCDをエアチェックしたりしてるだけの、平凡な高校生。
なんでユウがそんな僕に悩み事を打ち明けてるのか、さっぱり理解できなかったのだけど、次の彼女の言葉はそんなつまらない謎を氷解させるのに十分だったんだ。
「未来くんは・・・ご両親から星の研究とかしろって言われたりしない?それってすごく羨ましいなって・・・」
そうか、それは僕ではなく、僕の両親を透かしてみた言葉だったんだ。
そう思った瞬間、僕はなんだかたまらなく切なくなった。
僕の両親は、いわゆる宇宙開発の分野で一年の半分はヒューストンにいる。
正直、両親は僕の進路には至って興味がないようで、僕も一言だって相談をしたことはなかった。
もっとも、深く考えていなかったってのが一番の原因なんだろうけど。
ただーそうにしたって、なんだか初めて自分を必要としてくれたと思った相手が、実はそうじゃなかったってのは、僕が思う以上にたまらなくショックだった。
別に必要とされたいなんて思ったことはないけれど・・・どうでもいい、っていう感情は、誰かに嫌われるよりもずっとずっと堪えるんだということを、僕は初めて知った。
結局、僕がいえたのは一言だけ。
「そういうこと聞きたいなら、オレじゃなくて、親に直接聞いてくれればいいよ。オレは雨宮には必要ないじゃん・・・」
ビニール傘を置いたまま、僕は彼女の手を離し、席を立って雨降りしきる渋谷のセンター街へと飛び出した。
冷たいように見えた雨も、ユウの手よりはずっと温かいような気がした。
情けないよな、そう僕は何度も口に出して雨の街を走った。
なんだか、世界中の誰にも結局相手にされないガキなんだよ、と歩いてる人から笑われてるような、そんな気分。
道の端に微かに色を添える青い紫陽花が、不意に滲んで、やがて後ろへと流れていく。
結局濡れたまま僕は家に着き・・・案の定というか、体をたっぷり冷やしたツケが次の日に回ってきた。
ピピッと無表情な音を立てた体温計には、38.9℃という数字がチカチカと点滅していた。
僕は、学校に熱のため休む旨を電話で告げて、気だるい体を引きずりながら再びベッドへと潜り込む。
窓の向こうでは、夏が来るのを拒むかのように、薄暗い雲の群れがひたすら空の青を押しとどめていた。
いざ眠ろうとしたとき、ガタンと玄関で音がした。
「ただいまー、未来いるの?熱あるっていうから心配しちゃったじゃない」
重たい鉄製のドアをきしませながら入ってきたのは、姉貴だった。
「おかえり、デートどうだった?」
「うーん、雨降っちゃって結局ずっとお茶飲んでた・・・ってコラ、あんたにデートって言ってないじゃん」
ごつんと可愛い弟の頭を容赦なく叩いた姉貴は、僕と3つ年が離れている。
少しだけ外にカールした素直なロングヘアの、如何にも上品そうな顔立ちとは裏腹に、中身は結構あのシーザーと比肩できるくらいの横暴さを持ち合わせているとかいないとか。
ブルータスな立場の僕は、いつか下克上を・・・という冗談はさておき、僕と姉貴は、世で言う姉弟の中ではそれなりに、というよりはかなり仲のいい部類に入ると思う。
あまり真剣な話をしたことはないけれど、僕も姉貴も意外と二人でどこかに出かけることもあったし、姉気がが母親との間のいい緩衝材のような役回りを立ち回ってくれることもあって、それなりに頼りにしてる人だ。
もっとも、そんなこと姉貴に言ったら絶対に調子に乗るか、頭おかしいんじゃない?とか言われるに違いないのだけど。
「それより、あんた熱はもういいんでしょうね?」
「うん・・・だるいけど。朝帰りの姉ちゃんに心配されたくないなあ」
「本当に可愛くないヤツ・・・別に秘密にすることなんてないわよ」
そう言いながら姉貴はプラダのケリーバッグを乱雑にテーブルへと乗せて、そのまま台所へと立った。
やがて、お酒の甘い香りがプンと空気を支配する。
「玉子酒つくってあげるから、ちゃんと寝ていなさいよね。わたしにうつされるのが一番困るんだから」
ブツクサいいながらも、姉貴はせっせと手際よく玉子酒を準備し、ダイニングでおとなしく座っていた僕にトンと音を立ててマグカップを置いた。
もう体の方はそんなに熱っぽくはなかったけど、こうやって不意に優しくされると意識してないところから涙が溢れてきそうで、僕は慌てて外を向きながらまだ熱い玉子酒をすすった。
一口、二口と飲むうちに、じんわりと体中が発汗していくのが分かる。
それは、不思議と心の中にまで沁みていくような気がして−僕は、心の壁ってやつも意外と細胞壁と同じような構造なんだろうな、と授業で習った細胞壁の図を思い描いてみた。
「姉ちゃんはさ、どうやって進路とか決めた?」
まだじんわりと熱を持ったマグカップを片手でまわしながら、僕は姉貴の目を見ないままそう呟くと、姉貴は少し間を置いてこう答えた。
「・・・進路ってさ、嫌な言葉よね。
別に進むべき道なんてどこにもないのに、まるで道があるような言い方するから。
生まれたときは確かに無限の可能性を秘めて生まれてきたはずなのに、結局何もない道を、色々な制約の中で歩いてきただけのような気がする。
わたしもね、あんたも知っての通り大学に進んだけれど、特にやりたいことを決めて専門を決めたわけじゃないの」
姉貴の専門は、デザインと認識論が融合したような分野らしいんだけど、前に話を聞いたときはチンプンカンプンだった。
その話を聞いたとき、「人の認識という切り口からデザインを考えていくと、デザインってのは単なる芸術に押し留めるのは勿体無い、非常に理知的な分野の学問だということを再認識するわ」なんてことを言ってた覚えがあるのだけど。
「大事なのはね、今の時点で進むべき道が思いつかないというのも、立派な意思だってこと。勿論それを隠れ蓑にしたらいけないけれど、自らの意思で全ての可能性を追求することは悪いことじゃないわ」
そして、姉貴は片目をつぶり、こう付け加えた。
「今のは、お父さんの言葉の受け売り。可能性を絞らないことも、また無意味に絞り込むことも、同じくらい価値のないことなんだって」
「でも、オレやりたいことなんて思いつかないしさ・・・誰かが必要としてくれるとも思えないし・・・なんかヤだなあ、こんなのって」
珍しく弱気な僕に目を細めた姉貴は、ツカツカと立ち上がり、僕の頭をぐしゃぐしゃとかき回し、こう呟いた。
コツ、コツと時計が規則正しく秒針を刻む音が妙に大きく聞こえる。
「そんな偉そうな弟なんて要らないわよ、わたしは。誰かのために生きてるわけじゃないじゃない、未来だってさ。
自分のために生きて、その中で助けられるときがあれば助ける、助けて欲しいときがあれば助ける。
家族だってそうよ。そういうときのためにわたしやお父さん、お母さんがいるんじゃない」
「・・・うん」
殊勝に頷いた弟の顔に満足したのか、姉貴は照れくさそうに髪の毛をかきあげ、シャワールームへと姿を消した。
やがて聞こえてきた水の音をBGMにしながら、僕は今の姉貴の言葉と、進む道を見据えて真っ直ぐに話をしていたユウの顔とを交互に思い返していた。
僕は、いつか誰かに必要だと思ってもらえる存在になれるのだろうか。
思えば思うほどに熱っぽくなる体を引きずり、僕は再びベッドへと転がり、目を閉じる。
夢の中で、僕は無限の可能性を持ったままの生まれたての赤ん坊へと還っていった。
次の日。
珍しく連日での雨模様。
やっと学校へと登校した僕は、6限目が終わるやいなや学校を飛び出し、もう一度渋谷へとやってきた。
制服姿のままで歩く渋谷は、ちょっぴり不思議な気分。
水の防御壁がまるで一人一人を隔離してるかのようにも見えて、いつも嫌いな雨だったけど少しだけスキになれそうな気がした。
ストライプブルーの傘の下に守られながら、昨日の天体望遠鏡売り場へと急ぐ。
傘の水を払い、望遠鏡に手を伸ばそうとしたとき、ふと人の気配を感じて振り向いた。
「・・・雨宮」
雨宮ユウが立っていた。
今日はブレザーの制服を着ているせいか、いつもの凛とした佇まいだった。
ただ、走ってきたのか、少し上気しているようで、慌ててる雨宮も珍しいな、なんて暢気に考えている自分が少しおかしかった。
「追いかけてきたんだ、未来くんを。ここに来るなんて思わなかったけれど」
「・・・親に連絡取れとかそういうの?だったらオレは悪いけど力になれないよ」
「そんなんじゃない、違うよ未来くん」
「いいから黙って聞けって!
オレは雨宮と違って、自分のやりたいこともわかんない、情けないヤツなんだ。
親が夢のある仕事してても、息子は何の夢も持っちゃいないんだよ。
親も自由に育ててくれてるのか、特に何もオレに要求したりもしないのが、正直悔しいんだ、いつも。
そんなオレに雨宮みたいなヤツがあれこれ言っても、眩しすぎるだけでさ・・・辛いんだよ」
一気にそう吐き出すように言って、ユウの方を垣間見ると、彼女は意外にもその上気した表情を崩さず、僕の目をただじっと見ていた。
「だから違うの・・・別にご両親に話を聞きたかったとかじゃない。
勿論そうできたらうれしいけど・・・わたしは未来くんと話をしたかったの。
正直言うと・・・わたしがこうやってやりたいこと決めたのは、両親が反対するの分かってたから・・・それだけなんだと思う」
「え?」
「だってこんな年でそんなやりたいこととか決めちゃってる人の方がおかしいと思うもん。
悩みは違えど、同じように私以外の人だって悩んでるんだってことが分かって、ちょっぴりほっとしたんだ。
未来くん、いつもやりたいことを真っ直ぐにやってるような気がしたから・・・そんな人でも悩んでるんだーって」
そう言うと、ユウはちょっぴり複雑そうな表情を浮かべたまま僕から目を逸らした。
だんだんと、昨日見た防御壁の薄い表情へと帰っていくみたいに見える。
「オレ、そんな風に見えてたんだ」
「うん・・・といっても、クラスの女の子たちがそう言ってただけなんだけどね。
未来くんって、迷わないでやりたいことやってるような感じだよねって。
そんな人に偶然会って、つい甘えちゃっただけなの」
そう言いながら笑うユウの向こうには、どんよりとした雲を押しのけて青い空がチラチラと顔を覗かせているのが見える。
誰かのために生きるわけじゃない。
でも、自分がそれを忘れない程度には、誰かに必要とされたい。
そう思うから、僕たちは迷うんだ・・・
それに気付いたとき、僕はふと憑き物が落ちたような気がした。
親に、じゃなくて、僕と話をしたいという彼女の言葉がなんだか嬉しくて、僕はその感触を忘れたくないな、とその瞬間ひたすら願ったんだ。
その感触を、その生まれたばかりの情熱を忘れたくないから。
僕は傘を畳みながら、天体望遠鏡を買うために店員に向かって手を上げた。
あれから数年が経ち。
僕は、結局両親の分野とは全く関係のない、法学を専攻し、大学卒業後は潰しの利く営業職を選んだ。
ユウはどうやら夢だった宇宙開発センターへの勤務が決まったみたいで、年に2、3回ほど細々とメールで連絡が来る。
あの後、別に彼女との関係が変化したわけではなく、たまに望遠鏡の話や星の話をしたくらいだった。
結局、いつだって思うようには道は開いてくれないし、小説のように輝かしいエンディングが待ってるわけでもない。
それでも、何もないこの場所には、今だって無限の可能性は残ってるんじゃないか、と年を経るごとに思うようになれたのは、ちょっぴり幸せなことだなって僕は苦笑いするんだ。
ただ、一つだけ変化したことがある。
やっと自分が生きていきたいと思う道を見つけたような感触を掴んだことだった。
それは残念ながら今の仕事ではなく、大学時代に学んだ法学の延長で、新しい宇宙法の模索をしていきたいという想いだった。
大学にいたときには、やりたいことというより半ば気だるい義務感のみに突き動かされていた法学の世界も、こうして不思議と有機的に今までの人生と絡み合いながら収斂していくというのが、とても不思議なことだったのだけど。
未だに独身貴族を謳歌している姉貴は、たまに僕の家に顔を出したかと思うと、あれこれ面倒ごとを持ち込んでくる。
大抵は自分でセッティングのできない家電やPCの操作だったりするのだけど、その時々に彼女はこう付け加えるようになった。
「ね、未来のこと頼りにしてる人がいるってウソじゃないでしょ。ま、便利屋さんだけどね」
「便利屋って何だよ・・・」
僕は苦笑いしつつも、その言葉を受けるたびにベランダのそれに目を向けた。
今でも、あの天体望遠鏡は、白いその姿をずっと遠くの星に向けて起立している。
−恋にもならなかったあの日の感触と、ほんの少しの情熱を消さないように。
今日も僕は、天体望遠鏡の向こう側から、未だ来ない道の果てを見つめ続ける。
| 2005 |
| 04,02 |
| 2005 |
| 03,07 |
«東京タワー»
カレンダー
プロフィール
カテゴリー
最新記事
(04/18)
(03/17)
(02/15)
(12/15)
(11/15)
最新TB
ブログ内検索